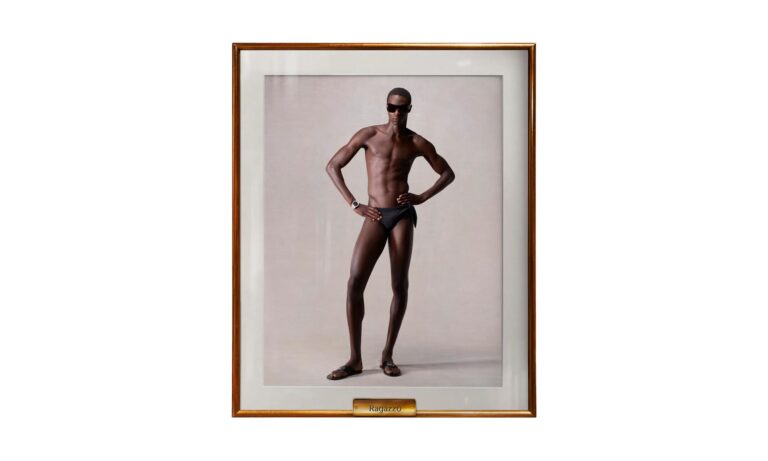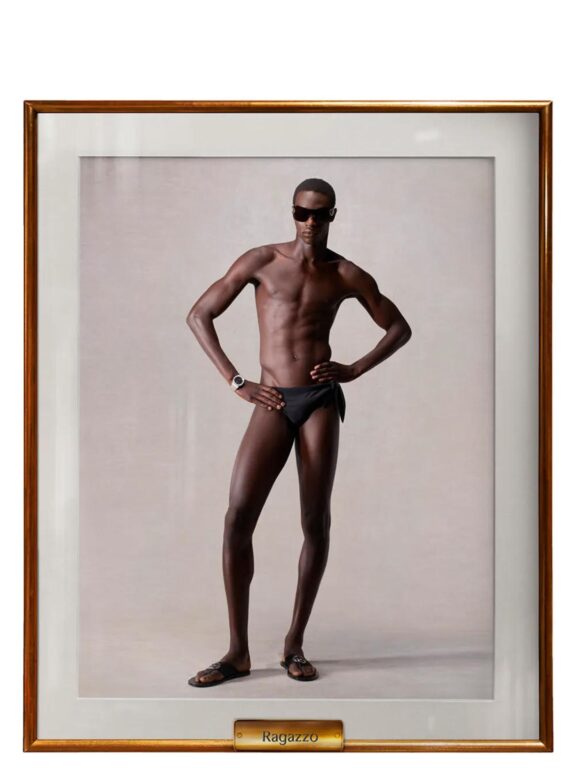life
Acne Studios、デザイナーインタビュー 新しさへの渇望と犠牲
「Ambition to Create Novel Expressions(新しい表現を創造する野望)」。その名のごとく、20年以上もの間、ファッションという激流に呑み込まれることなく、新しさを渇望し、全てを捧げ、創造し続けている。これが「Acne Studios(アクネストゥディオズ)」が常に「現代種」である所以だと語るのは、デザイナーのジョニー・ヨハンソン(Jonny Johansson)。
昨年11月にAcne Studiosの本社は、ブルータリズムが息づく旧チェコスロバキア大使館に引っ越し、ブランドとして新たなスタートを切った。アトリエからライブラリー、カフェテリアと全てを一戸の中に置き、部署ごとの壁をなくすことがブランドのクリエイティビティにつながると、ジョニーのハートフルな声が、冷酷さ漂うブルータリズム建築に響き渡る。
——100着のデニムからスタートした Acne Studiosも20年以上続いています。「新しい表現を創造する野望」を持ち続ける意欲はどこから湧いてくるのですか?
全てを犠牲にすること。全てのアイデアを捧げることが、次への原動力になる。常に動いていたい。流れる水のように。新しさを探求するための犠牲という行いこそがこれまで続いている理由だと思う。
——常に新しさ、モダンさを求めている印象がAcne Studiosにはありました。でも、ブランドが歴史を重ねれば重ねるほど、それはどんどん難しくなっていくのではないでしょうか。
そうだね。デニムからスタートしたのは、ストリートウェアやクチュール、そのどちらでもあるからこそ、常に新しさを模索できる完璧なキャンバスであると考えたから。それが、我々が「現代種」であり続ける所以。そして、それには犠牲が伴うということ。犠牲なくして「動」はないからね。
——動き続けたAcne Studios。ブランド創設当時と今で心境の変化はありますか?
今となっては大きな怪物と化したブランドが僕を呑み込もうとしている。だから走り続けなきゃいけない。それは、冗談だけれど(笑)。昔と比べて今は、より大きなプレイフィールドがあり、夢を掴むデザインの可能性の幅が広がっている。今はテキスタイル専門のチームにプラスチックを渡して、プラスチックを使いたくないと言えば、ウールやシルクで提案してくれる。パリでの生地調達もブランドのおかげでしやすくなっている。
——今の夢は何ですか? もしくは目標は設定していますか?
目標は設定しないことにしている。目標を達成した時には賛美するけれど、僕は次へ進みたいんだ。自分がしたこと、自分が作ったものに飽きてしまう。出来上がってすぐの洋服を着ることはないんだけれど、数年経って着ることはある。作っていく過程や未来に出来上がるものを想像するとワクワクするんだけれど、完成した時にがっかりして、「よし、次!」って感じになるんだ。そういう意味では、典型的なファッションデザイナーとは違う。制作過程を共にする仲間がいて、試練を与え、与えられることに喜びを感じている。
——今回引っ越しをしたこの場所は、仲間と共にチャレンジできるように、ファッションスクールをテーマにしたと伺いました。
そうなんだ。部署同士がより近くに感じられるようにしているのがポイントなんだ。より効率的に、デザインの可能性を広げてくれるはず。前のオフィスは狭かったから僕の本が散らかっていたんだけれど、今は大きなライブラリーがある。北ヨーロッパで一番のライブラリーにしたいと思っている。まだ並べ始めたばかりで、地下にもたくさん本があるんだけれど、どうやったらこのライブラリーが機能するかを考えているところ。本はとても重要だからね。新しい人が入ってきても、本のセレクションを見れば、僕のヴィジョンを共有できる。クリエイティビティを言葉でやり取りするというのは、とても難しいことなんだ。だからこそ、ライブラリーはこの建物の心臓部といっても過言ではない。
——ライブラリーの本が全てアルファベット順になっていました。
もちろん!さもないと、探すのが大変になるからね(笑)。みんなあそこで仕事をする。持ち帰ってもいいし、コピーもできる。
——日本の本もありました。ジョニーさんが実際に買ったものですか?
マグナスという男性が、本集めをサポートしてくれている。彼に考えを伝えると世界中から探してきてくれるんだ。日本の本は、いろんな美学が詰まっていて好きだよ。
——具体的に日本のどこが好きですか?
日本の色彩が特に好きなんだ。それから、日本とスウェーデンは似ているところがたくさんある。例えば、木製のものが多かったり、コンクリートや機能性、モダンさミニマルさへの嗜好もよく似ている。サウナもね(笑)。
今年の夏に3週間ほど日本に滞在していた。ほとんどが東京だったけれど、宮崎にサーフィンをしにいったり、京都、直島も訪れた。飛行機も使ったけれど、ほとんど鉄道を使って移動したんだ。
——何かデザインアイデアを刺激するものはありましたか?
京都のある草履屋の下駄が、丸を二つに割ったように作られていて素晴らしかった。東京には何度か行ったことはあるけれど、京都は仰天の連続だったよ。とても美しい。

——先日、ジュエリーブランドの「All Blues(オール ブルース)」のデザイナーと日本で話をしていて、Acne Studiosとのコラボレーションについても伺いました。コラボは彼がまだ大学生の頃だったと。若い才能とのコラボレーションはブランドが大きければ大きいほど、とても勇気のいる行いだと思います。
若い才能をサポートすることは特に重要だと思っている。今は、「Mulberry(マルベリー)」とのコラボレーションが展開されているけれど、多様で普遍的なブランドとAcne Studiosは何か面白いものが作れそうだと思ったから。そういった予想外のコラボレーションもしたいんだ。
——創造への野心を持つことは、これからの時代、AIやテクノロジーが発展する未来において、とても重要だと思います。それをファッションがサポートしてくれると思いますか?
同感だ。ファッションは人間にとって一番重要なものだと思っている。セックスよりもね。ファッション狂、政治以上かもしれない。
——アートに関してはどうですか?
もうそこまできている感じはあるけれど、ファッションほど大きな流れではない。自己表現をする上で最も簡単な方法であるから。洋服がアートの面白さの一端を担うべきだと思う。
——クリエイティビティの重要性を身近に感じてもらう。メディアもそのサポートをするべきだと思います。
たまに、「あなたはとてもクリエイティブな人ですね!」と言われるのだけれど、僕は全ての人がクリエイティブだと思っている。全ては、自分のクリエイティビティに耳を傾けられるかどうか。それを表現し、模索し、失敗しなければいけない。だから自身をクリエイティブだと思っていない人はあまり好きじゃないかな。
——自身の声を聞くことが難しいと思う人達に対して、どのようなアドバイスをしますか?
「Do rather than Think(考えるより先に行動する)」。例えば、才能ある若いグラフィックデザイナーは、尊敬するアーティストに取り憑かれている。彼、彼女らの作品にのめり込みすぎて、枠に囚われてしまうことがある。何も考えず、まず始めることが大切。最初は納得のいかないものになると思うけれど、始めないことには何も始まらない。表現することを恐れてはいけない。そういう意味では、ファッションは手軽に(自己表現を)始められるいいツールだと思う。
——自己表現、クリエイティビティを追求する上で、経験が邪魔をすることはありますか?
それは逆だと思う。時間が面白い人達との出会いを引き寄せてくれる。クリエイティブであるということは、自分のためではなく、人とのコミュニケーションであること、愛を共有するということだから。

——サステナビリティは今のファッションには欠かせないテーマになっています。
長年取り組んでいるプロジェクトではある。2008 年の「ニュースタンダード」というコレクションでは、パターンや縫製をシンプルにし、デザインを標準化するというものだった。自転車ブランドの「Bianchi(ビアンキ)」とコラボして、自転車の使用を促した。そのほかにも、様々な取り組みをしていて、その全ての資料を君に渡すことはできるけれど、Acne Studiosというブランドをそのテーマでプロモーションしたくないと思っている。なぜか。これは非常に重要なテーマであるから、純粋である必要がある。売るためのツールではない。ファッション業界にいる身としては、とても複雑なテーマであるのは確かだ。ただそれがブランド化していくことに不安を覚えている。売れる、売れないはデザインで判断されるべき。サステナビリティはシンプルに当然のことだから。
——マーケティングのツールとして扱われるべきではない。その通りだと思います。マーケティング至上主義の現代社会ですからね。
需要に対する何かではなく、自分の中にあるデザインが世の中に影響を与えた時こそ、価値のある瞬間はない。
——今日はなかなかお会いできないジョニーさんと話ができて楽しかったです。
難しい質問ばかりで、答えを出すのに時間がかかったけれど、本当はインタビューを受けるのは好きなんだ。ただ、答えが見つからない時があるから。
——答えがない時があってもいいと思います。
そうだね。僕はとても人間らしいってことだね(笑)。

- Photography: Yuki Kumagai
- Models: Ryusuke Tanamura & Saya Sugimori
- Interview & Words: Yuki Uenaka