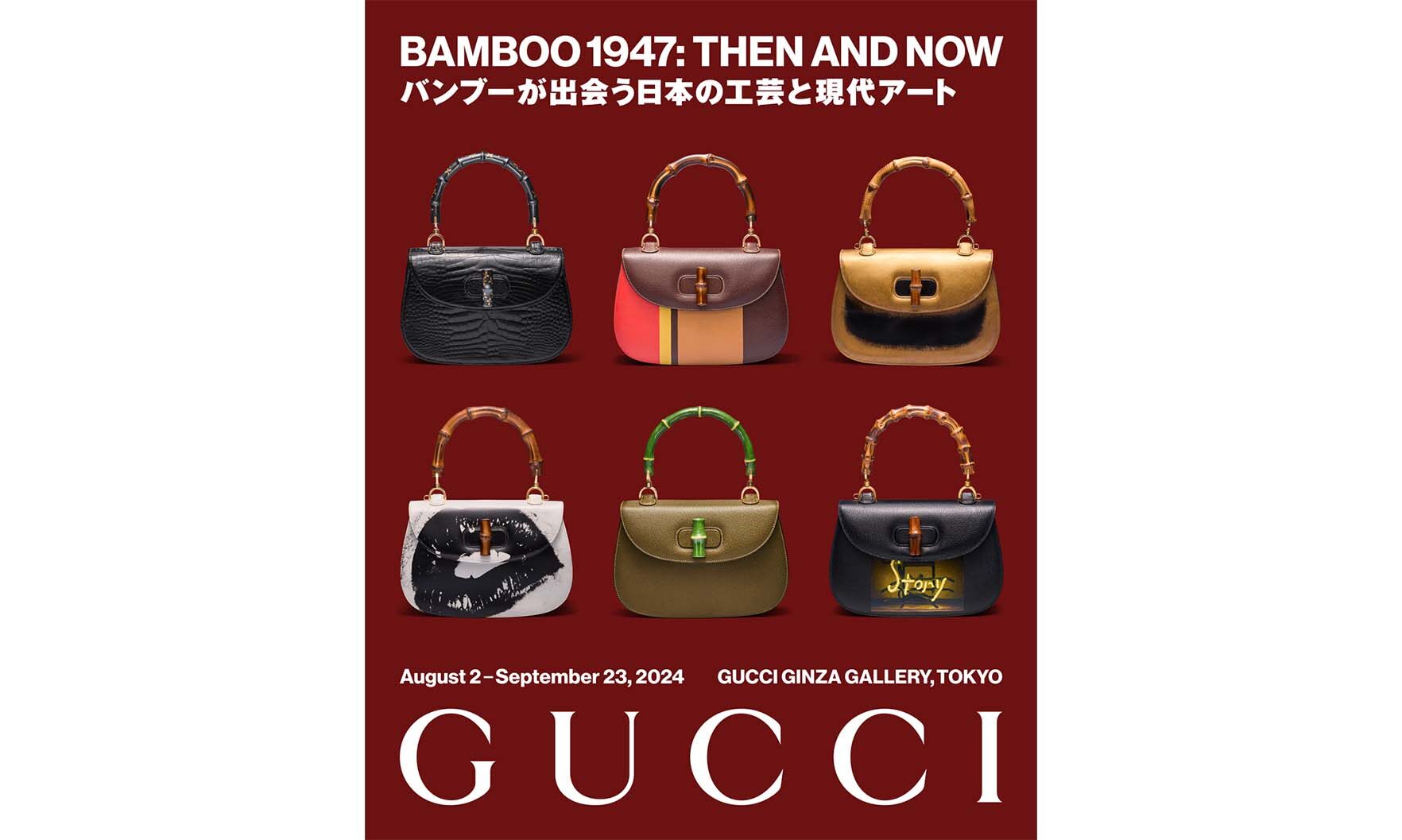JOHN LOBBの知られざる歴史 来日のデザイナーが語るブランドの本質

靴の王様。革靴のビスポーク専門店の頂に君臨する「JOHN LOBB(ジョンロブ)」。成功者が身に着ける最高峰の靴とも形容されるほど、高級で少しお堅い英国紳士のイメージもある。1849年創業から続く、約170年のブランドの歴史がそのイメージを確固たるものにしているが、2014年にパウラ・ジェルバーゼ(Paula Gerbase)がアーティスティック・ディレクターに就任して以降、スニーカーやワークウェアシューズなどを発売し、JOHN LOBBに新しい風をもたらしている。果たして新しい風はブランドにとって必要だったのか? いや、必要ではなく必然だったと確信したのは、パウラが解き明かしたJOHN LOBBの核心に触れたから。
共に訪れた杉本博司創設の小田原文化財団 江之浦測候所で、建築とアート、自然とのつながりと自身のものづくりに共通点を見出しながら、JOHN LOBBの本質へと迫っていく。

——JOHN LOBBのアーティスティック・ディレクターに任命された時の心境は?
ファッション出身で、靴のデザインの経験はなかったけれど、学ぶ自信はあった。新しいことに挑戦して、前進していくタイプの人間だから。Savile Rowでインターンから働いていた時もそうだけれど、不思議なことに何も知らずにゼロから始めるということにそそられるの。何も力になれないと感じることがとても重要だと思う。
JOHN LOBBのアトリエに入った瞬間に、学んでいきたいという自信が湧いてきた。質問を繰り返し、勉強していくと、私の仕事はJOHN LOBBを「話す」ことではなく、「聞く」ことだと気づいたの。そしてJOHN LOBBが生まれたイギリスのコーンウォールでリサーチをした。ジョン・ロブという人物やブランドが生まれた背景について。
——そこで、初代のジョン・ロブがロンドンまで400kmの道のりを歩いたという情報を手に入れたんですね?
そうなの。私の中のジョン・ロブは、英国紳士の中の英国紳士で、ウィスキーを飲んで、シガーを吸ってというイメージがあったのだけれど、JOHN LOBBのアーカイブに、テニスシューズやクリケットシューズなどのスポーツシューズやワークシューズをたくさん発見した。彼は農家の息子で、足の骨を折ってから足が不自由になり、父親が隣町で靴職人の修業を始めさせたのが始まり。そして、1850年代も21歳の時に自身のブーツを作りロンドンまで歩いていったというの。あの時代にどこに行き着くのかも分からない、何もかもを捨て、夢に向かって冒険をした。こんなに凄まじい始まりはあるだろうか?
みんなが思っているJOHN LOBBのイメージは大都市の英国紳士。だけど、漁師町の農家の息子が旅に出たという新しい冒険というイメージになった。みんなが持つイメージ通りの靴を作ることで私の仕事はとても簡単なものになるだろうけど、私はこのブランドの本当の物語を伝えていく義務があると感じている。

——パオラさんがJOHN LOBBのアーティスティック・ディレクターに就任した際に、多くのメディアが “新しい風” という表現をしました。それはブランドが本来持つ「冒険」というキーワードを体現しているという意味では、理にかなっていると思います。でも「靴の王様」なるJOHN LOBBのイメージ……
そう、そのイメージを持っている人からすると、ウォーキングシューズやハイキングブーツを作ることが衝撃なのかもしれないけれど、面白いことにJOHN LOBBの英国紳士のイメージはブランド創設からずっと後のこと。もちろんそれもブランドの歴史の一つとしていいのだけれど、本質は冒険で得る発見だということ。そして現在は、様々なところに旅できる時代。ジョン・ロブが成してきたこと、作り上げてきたものは、今以上に生かされることはない。
漁師町に残ってブランドを作ることもできたのかもしれないけれど、今のままではいけないという何か抗えない本能に身を任せて冒険をした。こうして日本に来たこともとても刺激になっている。
——例えばどんな刺激ですか?
京都に行った時に、その日に運良く入れたお寺があったの。一緒に行った友達に「間」についての説明をしたのだけれど、良く理解をしていなかった。「Empty Space(何もない空間)」だけれど、それは空っぽではなく、何かが詰まっている。感情、有意義な何か。もしくは、静けさが、発する言葉よりも重要だという考え方。
——シェイクスピアも「静」の重要さを説いていました。
そう。効果を与えるために必要なもの。
——そして、ファッションも同様にネガティブスペースを捉えてデザインするという意味では同じと言える。
まさにその通り。デジタルの発達で、リサーチも簡単にできるようになった社会なので、やはり実際に身をもって体験したことをデザインに落とし込まないと、本物とは言えないと思うの。
——この時代だから特に大事ですね。
そう、オレンジの香りを嗅いだり、シンプルに人間らしくいたりすること。デジタルがもたらしたコミュニケーションのスピードや人とのつながりはもちろん素晴らしいことだと思う。
——コントラストが大事。
そうね。みんなデジタルと人間らしさのコントラストに気づき始めている。デジタルは手段として素晴らしいけれど、会話や体験、人間らしさの部分が人生にとって意味のある瞬間へと結びつけてくれる。これが「質への気づき」だと思っている。

——都市と自然ではどちらが好きですか?
ブラジルに生まれて、アメリカのボルティモアに移住し、イギリスに勉強をしにと、どこがホームかを決められないのだけれど、どの都市も自然に囲まれているから、自然の中にいると落ち着くの。でも、混沌とした都会の美しさを忘れて森の中で住むとなったら最終的には飽きてしまうかもしれない。
建築をする際の環境の日本の捉え方は他の国と違っている。例えばフランスの建築はその土地を支配するように建てられているのに対し、江之浦測候所の建築は、確かにこの土地を支配しているように見えるけれど、本来の自然が生かされるような部分をあえて残しているよう。石畳を見ても、全て完璧に並んでいるけれど、ひとつひとつの石に目を向ければ、自然のまま、不完全さが見えてくる。この不完全さのバランスが素晴らしいラインを作っている。フランスの庭園は、左右対称で完璧だけれど、どことなく人間の力で自然を支配しているように見える。だから、日本は人間と自然の調和がとれていると思うの。
——草木が石畳や石の壁を伝って成長しています。時が経つにつれて変化するデザインになっているのも、自然との調和ということですね。
自然の赴くままをある種操作するという行いは、良いデザインだということ。主観で価値を足していくのではなく、至極シンプルな意味のある選択をする。
——JOHN LOBBの方向性と似た部分を感じますか?
本当にそう感じる。最高の素材を使うにあたって、その最高の素材自らが語るデザインではなく、デザイン欲求のためにあれこれ付け足すという作業とも違う。最高の素材が本当に輝けるプロポーションやディテールという環境づくりをしている。
——「JOHN LOBBの靴を買ってもらってからが旅のスタート地点だ」ということもおっしゃっていましたね。タイムレスな環境づくり、ものづくりもJOHN LOBBの代名詞となっていますね。
ここにいて感じるのは、建って間もないのにタイムレスで歴史を感じられる。何千年先を見越してのデザインが垣間見えるの。新しいかたちで、そして予期せぬかたちでフレーミングされている。これは JOHN LOBBでの私の仕事に重ねられると思う。必ずしも私という個性をいつも出さなくてもいい。JOHN LOBBの歴史の中から革やディテールなどを見つけ出し、その美学をシンプルに現代に投影する。デザイナーとしては、その美学への最低限の自身の介入はとても難しいことなの。なぜなら、個性の塊であるデザイナーは無意識に自身の影を追ってしまうから。
この場所の本質は、支配に対する抑制が作り上げたことなんじゃないかしら。建築物に人の手を感じることはあっても、支配的なものを感じない。デザインをした人の選択が見えるだけではなく、その周りの自然も同等にフォーカスされている。私はデザイナーとしてとても感銘を受けている。自身のエゴを捨てて、ピュアなものを作り上げる。そこには高潔さが時を超えて佇んでいる。それが、「私がデザイナーのJOHN LOBB」ではなく、「JOHN LOBBの本質」であると思う。
靴を買っていただくことは、最高の瞬間であるのは事実。でも私にとってそれは、店で起こった行いにすぎず、買った後のこれからの靴との歩みのほうが大切。その靴とどこに旅をして、どんな体験をし、靴そのものが何を刮目するのか。

- Photography: Seiichi Niitsuma
- Words: Yuki Uenaka