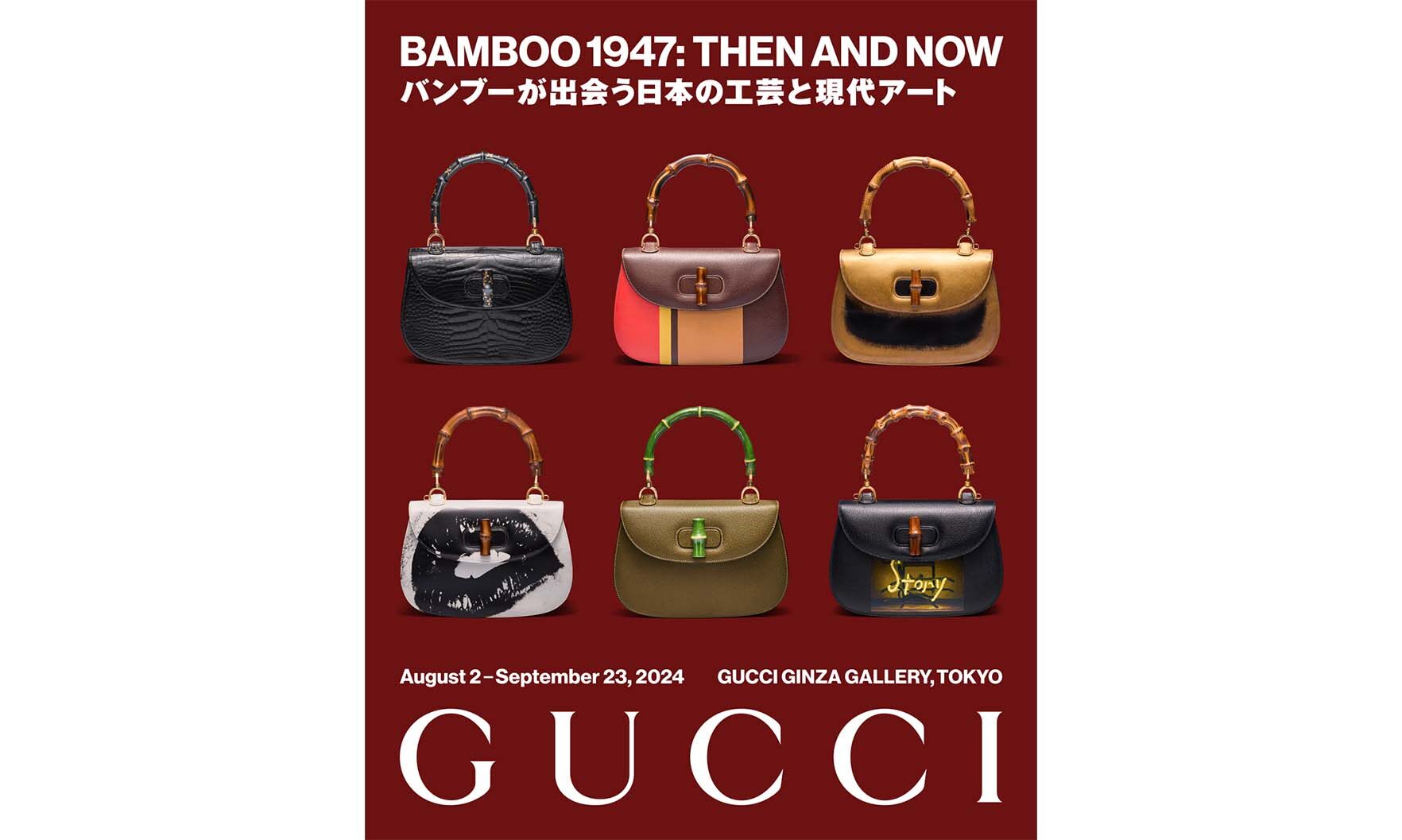4人の新進デザイナーが語るロンドンの近況

1940年代後半以降のファッションの仕事はある意味、パリのかび臭いクチュールサロンからいかに業界の支配権を奪い取るかをテーマとしてきたような部分がある。MARY QUANT(マリークヮント)やBIBA(ビバ)を生み出したモッズ、MALCOLM MCLAREN(マルコムマクラーレン)やVivienne Westwood(ヴィヴィアンウエストウッド)のパンク、ニューロマンティックスやクイアカルチャー、そこから生まれたAlexander McQueen(アレキサンダー・マックイーン)のイコノクラスム、ジョン・ガリアーノ(John Galliano)の歴史的ロマンティシズムと、ロンドンは常に大きな影響力を有してきた。セントラル・セント・マーチンズに代表されるロンドンのファッションスクールはクリエイティブ人材を育み続けている。またそれを絶えず支える独立系ファッションメディア、英国ファッション協会、気鋭デザイナー育成プログラムのNewGen、ファッション支援団体であるサラバンド財団と、ロンドンには健全な体制が常にある。
ロンドンには、成功するデザイナーを生み出すには環境が必要である、何もないところからは才能は生まれないという理解がある。超個人主義的かつ超商業的なニューヨークのような都市の場合、その点に心底納得、同調することは決してないだろう。ロンドンにはダンスクラブ、アートスペースが揃い、街並みも歩きやすい。クリエイターが街からエネルギーを得て、またそこから生み出したものを街に還元できる構造ができている。
ロンドンの活気に満ちたファッションシーンはこうした精神性からつくり出されたものだ。しかし課題もないわけではない。今日、ロンドンで活動するデザイナーが住む世界と、彼らが直面している課題をよりよく理解するため、4人の若手デザイナーの話を聞いた。

ネンシ・ドジャカ(Nensi Dojaka)
——ファッションデザイナーになろうと思ったきっかけは?
自然とそういう流れに。最初は建築を勉強しようと思っていたけれど、もっとクリエイティブな「自由」やファンタジーの要素があるものに挑戦したいと思うようになった。いくつか試した結果、ファッションを勉強することになった。
——美学の確立方法は?
最初はランジェリーのコースに通っていた。技術重視で、大枠のシルエットではなく徹底的にディテールを叩き込まれた。今の仕事の仕方は、そこから受けた影響が大きい。
——ロンドンでデザイナーの仕事をする利点は?
駆け出しの頃に多くの支援を受けられること。何10年も前から多くのデザイナーのキャリア発進を助けてきた土壌があって、そのお世話になってきた。
——若いデザイナーとしてどのような課題に直面していますか?
課題は多い。若いブランドの場合(巨大企業の場合は必ずしもそうではないけれど)常に何か光るものを持っていなければ、というプレッシャーがある。健全なビジネス構築を目指しつつ、常に新たな視点を見せなければならない。専門知識のない少人数のチームで一度に多くのことに取り組まなければならない。


——5年後はどうなっていると思いますか?
明確なアイデンティティと幅広い製品ラインナップを備えたブランドをつくり上げて、小売店などもできるようになっていたい。

アーロン・エッシュ(Aaron Esh)
——ファッションデザイナーになろうと思ったきっかけは?
母は彫刻家、父がミュージシャンで、自分自身も何かクリエイティブなことをしたいといつも思っていた。セントマーチンズのグラフィックデザインの学士課程に入ったものの、半年程度しか続かず、コンピューター仕事は無理だと気付いた。ファッションにも興味があったし、ラフ・シモンズ(Raf Simons)が大好きだったし、パリで穴開きジャンパー姿でスケートボードをする若者のビジュアルアイデンティティにもとても惹かれた。Alaïa(アライア)のガウンのようなものではないそういうファッションにとても共感した。それで27歳のとき、奨学金をもらってセントラル・セント・マーチンズのファッションプログラムに入った。予想はしていたけれど本当に大変だった。でもその厳しさは確かに必要だったと思う。ファッション業界で生きていくのは大変だから、そこでやっていけるだけの講座となると厳しくならざるを得ない。
ファッションという仕事について多くを学んだ。ファッションは、家やテーブルをデザインしたり、絵を描いたりするのと同じで、いろいろなコードやイメージに取り巻かれてものが完成する。少なくとも僕の場合はそういうアプローチになっている。
卒業後はとにかく怒涛のようで。2022年に卒業。卒業コレクションがSsenceに採用されて、それからLVMH賞のファイナリストに選出されて、9月にロンドンでデビューショーをしたばかり。


——美学の確立方法は?
個人的に好きなものと追究してつくり出す洋服は違う。好きなものはいろいろある。昔のAlaïaも好きだし、アッパークラス系のVINTAGE COCO CHANEL(ヴィンテージ・ココ・シャネル)のレディースも好き。ラグジュアリーなグラマーやシックなエレガンスと、ロンドンのような都会に住む20代、30代の感覚を交錯させるのが好きだ。昨シーズンは、それがさりげなく、上手くできたと思う。僕自身の友達の着こなしや僕ら自身が買っている物を思わせるコレクションでもある。まだ誰もしていない、すごく新しい感覚だと思う。しかも嘘がない。そこがすごく大事だと思う。気に入ってもらえるかどうかよりも。
——ロンドンでデザイナーの仕事をする利点は?
ロンドンは唯一無二の都市。若いデザイナーの街とか、装いについていろいろなものの見方を提供してくれる街、というイメージで好かれていると思う。他の都市には見られないような良いデザイナーがたくさんいて、活躍の場もある。ロンドン・ファッション・ウィークは若いデザイナーを応援してくれる。ブリティッシュ・ファッション・カウンシルのNewGenから資金面での支援を受けることもできる。僕達は今、サラバンド財団(アレキサンダー・マックイーンがロンドンの若手デザイナー支援を目的に立ち上げた財団)の建物内にスタジオを構えていて、仕事を後援してくれる多くの人達と関係を築くことができる。
それにロンドンという街にいれば、もうそれだけで、街角で良いファッションが見られる。金曜や土曜の夜は、道行く人の着こなしを、ライフスタイルコードとか、ビジュアルアイデンティティとして見ているだけで、リサーチをしているような感覚になる。僕のデザインの中核には、都市という存在があると思う。そこはとても大事な部分だ。特定のクラブだとか、人を参考にしたデザインも生まれるくらい。クラブじゃなくてもいい。コロナ禍以来、クラブに行く人も減っていることだし。でも夜中の3時にふと気が付くと友達の家で床はベタベタ。飲んでいるのは8ポンドくらいのプロセッコだけどみんな着飾っている、みたいな情景は、ランウェイで時々見る現実離れした世界よりも、すごくリアルに思い描ける。
——若いデザイナーとしてどのような問題に直面していますか?
莫大な資金を持たずに自分のできる範囲で小規模な事業をすることの難しさ。後ろ盾が十分ない中でブランド経営をするのはとても大変だ。競合は多い、手数料や諸経費もいろいろと飛んでいく、卸売りのシステムも崩壊している、そんな中で業界独自のカレンダーをこなさなければならないのは、規模の大小にかかわらず、どのブランドにとっても難しいこと。ファッション業界ほど、華やかさと現実の落差が両極端な業界もないと思う。
卸のシステムはもう通用しない。新しいコレクションを発表するためには工場に支払えるだけの資金がなければいけない。卸売り業者を通していると、入金まで1カ月かかったり、もっと言えばいくら待っても支払いが来ないこともある。そんなのを待っている時間はないんだ。Ssenseの支援はとても厚い。僕達のことをGoogleで発見してくれた。消費者への直接販売はまだしていないけれど、考えるべきかも知れない。フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)の例を見れば、D2Cが十分可能だという感覚は持てる。
——5年後はどうなっていると思いますか?
長く愛されるブランドを作りたい。5年後に誰かがVestiaire Collectiveで僕のブランドのジャケットを探していてくれたら嬉しい。それ以上の壮大な計画は立てていない。今は暖房が効いてミシンの置ける建物に居られるだけで幸せ。とても恵まれていると思っている。

レジーナ・ピョー(Rejina Pyo)
——ファッションデザイナーになろうと思ったきっかけは?
母がソウルでデザイン・スタジオを経営していて、身の回りに生地やスケッチがたくさんあった。そういうクリエイティブな環境で育って、アートとファッションデザインが大好きになった。子供の頃からお裁縫を学んで、自分でデザインをするようになった。大学卒業後は韓国の大手アパレル会社に就職したけれど、自分のブランドを持つことがずっと夢だった。雑誌やファッションショーを見ているうちに、有名デザイナーの中にロンドンのセントラル・セント・マーチンズの卒業生が多いことを知って、修士課程に出願し、ロンドンに移り住んだ。自分のブランドを立ち上げようと思ったのは、駆け出しの頃、ファッション市場には隙間があると感じたから。巨大なデザイナーズブランドはあまりにも高価で、私も友人も手が出なかった。ハイストリートは目先のトレンドに振り回されていて、品質も今ひとつだった。私としては、自分や友達が実際着られるようなものを作りたいと思った。良いものでありながら時代を超越したもの、良い品質でありながら手に入れやすいもの。
——美学の確立方法は?
私の目標は、特別な女性が日常的に着る特別な服を作ること。時が経っても廃れないラインナップをフルで出したい。アーティスティックな感性と、着やすさを両立することが私のスタイル。ファッション業界は刺激が過多になりがち。そんな中で私達のブランドでは、実際に着ることができて、タイムレスでありながら、女性であることの広がりとダイナミックさを追求した服作りに努めている。


——ロンドンでデザイナーの仕事をする利点は?
ロンドンはファッションデザイナーになるには素晴らしい街。美術館やギャラリー、建築物、食べ物から芸術まで、たくさんの刺激がある。街角で見かける女性達からも発想が湧くことがよくある。クリエイティブネットワークやメンターシップ・グループもたくさんある。ロンドンに住む人達は時間と知識を惜しみなく提供してくれて、常に新しいことを学ぶことができる。
——若いデザイナーとしてどのような問題に直面していますか?
セントラル・セント・マーチンズに入学するために渡英を決めたときにはあまり英語が話せなかった。卒業後間もなくHan Nefkans賞を受賞し、自分のレーベルを立ち上げる資金を得た。CSMではデザイナーとしての強みは伸ばせたものの、ビジネス面についてはあまり学んでいなかった。最初の頃は、生産、PR、販売、卸売、マーケティング……といったことを苦労して学んだ。最初の数年はとても大変だったけれど、徐々に会社が成長していった。
——5年後はどうなっていると思いますか?
昨年末、ロンドンのソーホーに初の常設店舗を開くことができた。お客様との直接のつながりも持てる。楽しいイベントやコラボレーションも準備しているところ。ブランドの世界リーチをさらに広げ、いろいろな都市でイベントを開催し、地域と関わりが持てるようにしていきたい。

シモーネ・ロシャ(Simone Rocha)
——ファッションデザイナーになろうと思ったきっかけは?
大学時代、発想を翻案し、感情を表現し、ストーリーを語る最良の方法は、服や布地、テキスタイル、手仕事だと感じたことが、ファッションデザイナーになろうと決めたきっかけ。
——独自の美学を確立した方法は?
家族、アイルランド、香港、アート、自然界など、インスピレーションの源は何度も訪れるが、常に人工的なものとモダンなもの、女性らしさと力強さのバランスを考えながら、力を与え、美しく、実用的な服を作っている。


——ロンドンで働く利点は?
ロンドンはギャラリーや美術館、建築物など、インスピレーションを与えてくれる場所のたくさんあるとてもクリエイティブな街。発想、アイデンティティ、文化のるつぼだと思う。
——若いデザイナーとして、どのような問題に直面しましたか?
若手デザイナーに重要なのは、自分のアイデンティティに忠実であり続けながら、そこから成長すること、そして良いチームを作り、周りの世界に対応しながら成長すること。
——5年後はどうなっていると思いますか?
人にインスピレーションを与えられるようなコレクションをつくり出していたい。
- WORDS: EUGENE RABKIN
- TRANSLATION: AYAKA KADOTANI