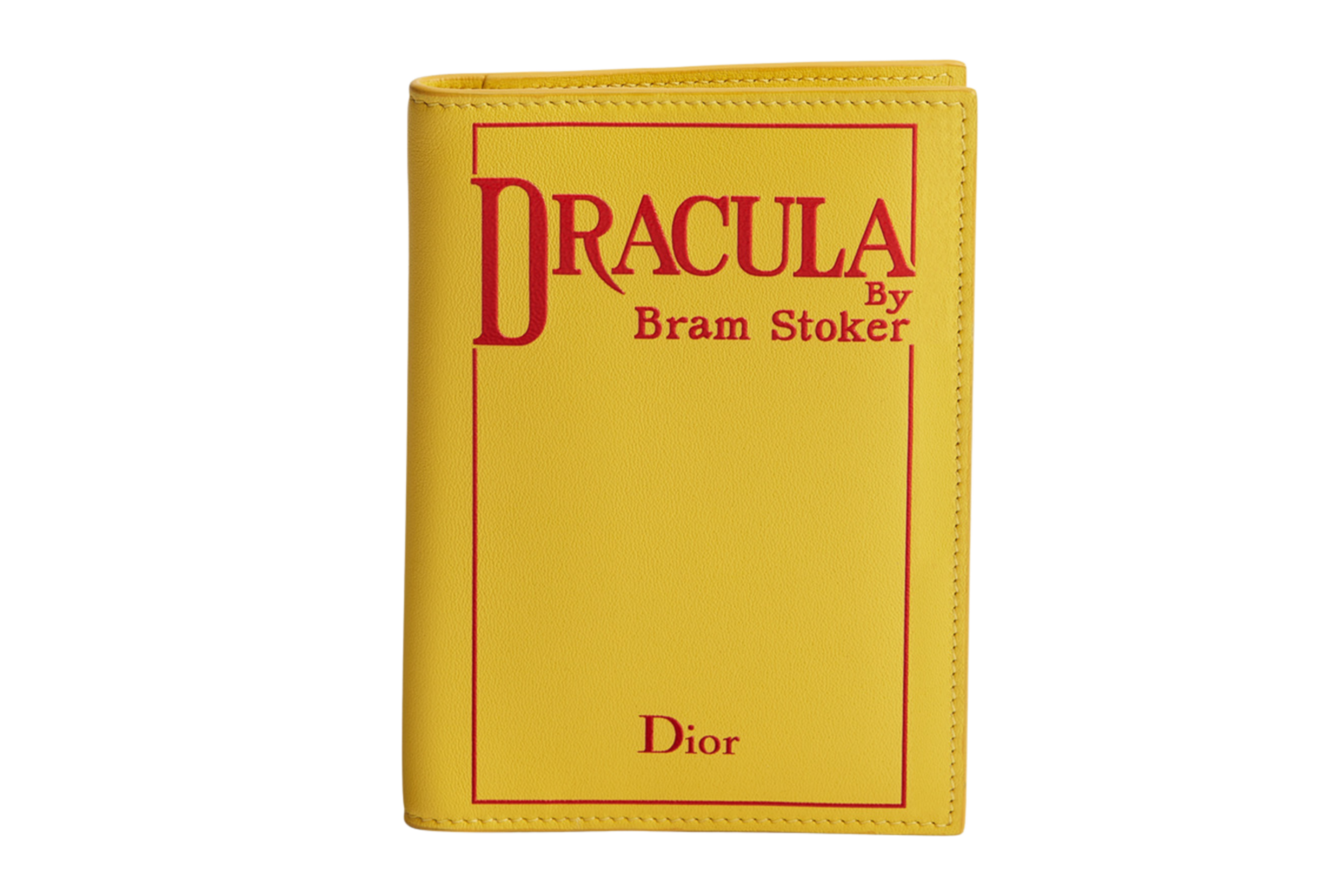DIOR


【Dior × 横浜流星】存在そのものがアートになる。
ジョナサン・アンダーソン(Jonathan Anderson)がクリエイティブディレクターに就任して、最初に発表されたDior(ディオール)の2026年サマーコレクション。バロックやロココなどの大げさな芸術が台頭していた時代の潮流に抗うかのように、日常の美や共感を描き出したジャン・シメオン・シャルダン(Jean Siméon Chardin)の静物画をメタファーに、ジョナサン・アンダーソンのファーストコレクションは、貴族的なコードにあらゆる崩しを加えたスタイルとなった。
象徴的な「バー」ジャケットをドネガルツイードで再構築し、合わせたカーゴショーツには1948年の「デルフト」ドレスのディテールを重ねた。メンズとレディースの境界を曖昧にしていく宣言とも感じさせるファーストルックに続いたのは、アーカイブのオートクチュールを再解釈したショーツやトラウザーズ。そして、気品あるウエストコートやレボリューションコートなど、Diorのアーカイブを賑わす貴族的なコードは、完璧さを回避するように着崩されたデニムパンツや紐のほどけたスニーカーと組み合わされ、ヌーヴェルヴァーグの登場人物のムードを漂わせる。
新しい時代に、この最新コレクションをまとったのは、映画『国宝』、NHKの大河ドラマ『べらぼう』で躍進中の俳優、横浜流星だ。次々、話題作に参加し、活躍のステージをどんどん広げながらも、伝統芸術に囲まれ、取り憑かれたように役柄を貪り現代を生きる。そのひたむきさの根底に潜むのは、強さと誠実さ。現代の芸術を彩る旬な作り手の苦悩と野望は、この世に豊かさと知をもたらす。

——Diorのクリエイティブディレクターがジョナサン・アンダーソンへと代わってから、日本で最初のメンズファッション撮影となりました。横浜さんはこれまで様々な側面からDiorの世界観を体感してこられていると思いますが、今回の変化をどのように感じていらっしゃいますか?
毎回、ショーに行くたびに、ひとつの作品を見させてもらっているような感覚がしています。今回は現地に行けなかったのですごく残念だったんですけど、いろいろと拝見して、着こなしの幅がグッと広がったな、というのは感じていました。
ジョナサン・アンダーソンのクリエイションは、Diorのヘリテージとともに、日常の美を讃えていますよね。そこには、伝統を大切にしながらも進化させていく「心」を感じますし、自分の普段着とは正反対なタイプのテイストなので、今回の撮影もすごく新鮮な気持ちでやらせてもらいました。新たなスタイルにも挑戦していきたいな、と思っています。
——着用いただいた中で、特に印象的だったルックはありましたか?
とにかく、全体的に、遊び心がちりばめられていたように感じました。襟をアンバランスにスタイリングしていたり、デニムの片裾だけをロールアップしたり……それから、ショールやネックバンドといった遊び心溢れる小物も多かったです。そのバランス感も印象的でした。「そういう着こなしがあるんだ」と、着るたびに発見や驚きがたくさんありました。


——いつもは、どんな私服が多いですか?
私服は動きやすさや機能性を重視しているかもしれないです。今後、今回のルックにもたくさんあったように、デニムを着用する機会も増えていくと思いますし、新しい発見や広がりがあると思うと、とても楽しみです。
——Diorの2026年サマーコレクションは、何気ない日常を切り取ったシャルダンの絵画をメタファーとしているように、様式と即物性といった対極的な世界を行き来しているのが特徴です。そこで、横浜さんには、俳優としてカメラの前に立つ「オン」の時間と、ご自身の「オフ」の時間。その2つの世界をどのように行き来し、ご自身のバランスを取られているか、まずお聞きできますでしょうか?
常にオンでいるのかもしれないです。俳優という仕事は、カメラの外にある日常の全てが活きるというか、繋がってくるので。家にいるときも、プライベートで外にいるときも、つい「何かに繋がるかもしれない」と発見を探して、常にアンテナを張ってしまうところはあります。ただ理想を言えば、きちんとオンとオフを分けないと息苦しくなるとは思っています。
——抜きどころがないと疲れてしまいますよね。
ないといけない、とは思っているんですけど、自分は未熟者だし、インプットしたいことがたくさんあるから、今はまだこのやり方でいいのかなとは思ってます。
——そんな中で、自分らしさに戻れる瞬間はどのようなときですか?
リングの中ではバチバチにやり合っていたのに、終わった後にお互いが分かり合っているような、そんな関係になっていたりもする。あれは、相手がいないと成立しないものだと思うんです。だからこそ、笑い合ったり、目で「やるな」と認め合ったりする瞬間に、すごく心を動かされるんです。必ず礼に始まり、礼に終わる。そして最後には抱き合って、お互いを称え合う。あの姿が本当に素晴らしくて、いつも心を打たれます。
格闘技を観ている時間は、少し仕事のことを忘れられる瞬間かもしれないです。ただ、格闘技にも選手それぞれの人間ドラマがあるので、そこに感情移入して「なるほど、人はこういうときにこんな感情になるんだ」と学ぶことも多くて。結局、またそれを仕事に活かせないかと考えてしまうんです。
——なんでも研究材料になるんですね。
人前には出ているけど、取り繕ってないからこそ、その生々しい感情が見える。だから、すごくこう……引き込まれるというか。
——格闘技を観ていて、一番心を掴まれるところは?
例えばキックボクシングだったら3分3ラウンド、総合格闘技なら5分3ラウンド。ボクシングはちょっと長くて、3分12ラウンド。その時間の中で、全てが決まってしまうんです。すごく儚い世界です。
でも、選手達はその数分のために、命を懸けて準備してきている。いわば、昔の武士と武士が命を懸けて向き合うようなもの。それで本当に、人生が変わってしまうことだってある。その覚悟を持ってリングに立つときの顔、そこに向かっていくときの表情、そして勝敗がついた瞬間の顔。それぞれに、強いものを感じます。

その役としてちゃんと “生きる” こと
——『国宝』や『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』など、日本の伝統や歴史を背負う大きな作品が続いています。取り組む上で、どのような覚悟で臨まれているんでしょうか?
どの作品も「これは大きい作品だから」とか「これは小さいから」と区別はせずに、ちゃんと覚悟と責任を持って取り組んでいます。スタッフ一同で力を合わせて、観てくださる方の心に響くものを届けられるように、というのは、いつも意識しています。
自分としては、その役としてちゃんと “生きる” ことが一番で、その世界の中で自然に存在できるように、というのが一番大事なことだと思っています。役作りに関しても、ちゃんとその人物として生きられるところまで持っていくっていうのは、当たり前だけどちゃんと大事にしているところです。
『国宝』のときは、1年半くらい準備期間をいただいていたんですけど、やればやるほど歌舞伎役者さんへの尊敬の念が深まるというか、自分なんてまだまだ足もとにも及ばない、と思わされました。ただ、 “大垣俊介”
として、今その場にいることとか、初めて舞台に立つときの気持ちだったり、瞬間瞬間をちゃんと “本物” として生きることだったり、感情の機微だったり、そういう部分は自分達役者にできることだと思っているんです。
こういう作品って、「歌舞伎役者さんがやったらいいじゃん」と思われたら終わりだと思うんです。だからこそ、自分達がやる意味っていうのはちゃんと考えなきゃいけないし、その上で歌舞伎の世界を描かせてもらうっていうことには、しっかり敬意を持って向き合っていました。
最近は大河ドラマとかでも、日本の伝統芸能や文化が描かれることが増えてきていますけど、そういうものを世に届けられるっていうのは、日本人として誇りに思います。


——横浜さんは役に合わせていくために、食べる物の嗜好すら変わるほど、役に入り込んでいくそうですね。
毎回、そうしています。自分は、引き出しの数が多いわけではないので。だから自分を排除して、これから生きる役の魂を自分の体に入れていくような作業が自分には向いているのかなと思っていて。
役を引き寄せていくことは、自分には難しい。だから、なるべくその役のことだけ考えるようにしています。体を貸しているような感覚でいると、日常生活での考え方や感じ方も、少しずつ変わっていくんです。
——自ら憑依させていく感じでしょうか。
そうですね。ただ、経験を重ねるにつれて、役と自分の距離感もはかれるようになってきました。今までは、役のことだけを考えて、現場では常にその役としていなきゃと思っていましたけど。最近は、客観性を持って俯瞰で見ることも大切にしています。
——その役作りはどのように身につけられてきたんですか?
自分から誰かに聞いたりもしないので、我流です。一番大事なのは、その人物として “ただそこにいる” という感覚です。もしかしたら現実のどこかに存在しているかもしれない、そう思えるくらい、その世界の中で生きられたらと思っています。空気のような存在として、自然に出てくるものに自分がなれていけたら、という意識でいます。
——過去の人物を演じるとき、 “自分とは違う時間” を生きる中で、コントラストによって気づきや学びはどう受け止めていますか?
毎回、自分とは違う考え方、生き方をしている人物を生きるわけで。例えば台本を読んでいても「俺だったらこうはしないな」とか、「あ、こういう言い方をするんだ」「こういうことができるんだ」っていう発見が、本当にあります。考え方ひとつとっても、全然違うなと感じます。
実在した人物を演じるときは、自然と感謝の気持ちが大きくなるんです。彼らがそれぞれの時代で道を切り拓いてくれたからこそ、今自分達が享受できている娯楽やエンターテインメントがある。そういうことも含めて、感じることは多いですね。
「蔦重」も本を通して世の中を少しでも良くしようという想いがあった。そういう姿に共感される部分もあるのでしょうか。
そうですね。自分もそうありたいと思う気持ちはあります。ただ、彼らのように生きられるかというと、自分にはなかなか難しい。でも、自分なりの形で、それに近いことができたらとは思っています。


【書誌情報】
タイトル:HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY RYUSEI YOKOHAMA
発売日:2025年12月19日(金)
定価:1,650円(税込)
仕様:A4変型
◼︎取り扱い書店
全国書店、ネット書店、電子書店
※一部取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。
※在庫の有無は、直接店舗までお問い合わせをお願いします。
- Photographer: Joshua Helius Noel
- Stylist: Go Negishi
- Hair & Make-Up: Akihito Hayami
- Words: Yuka Sone Sato