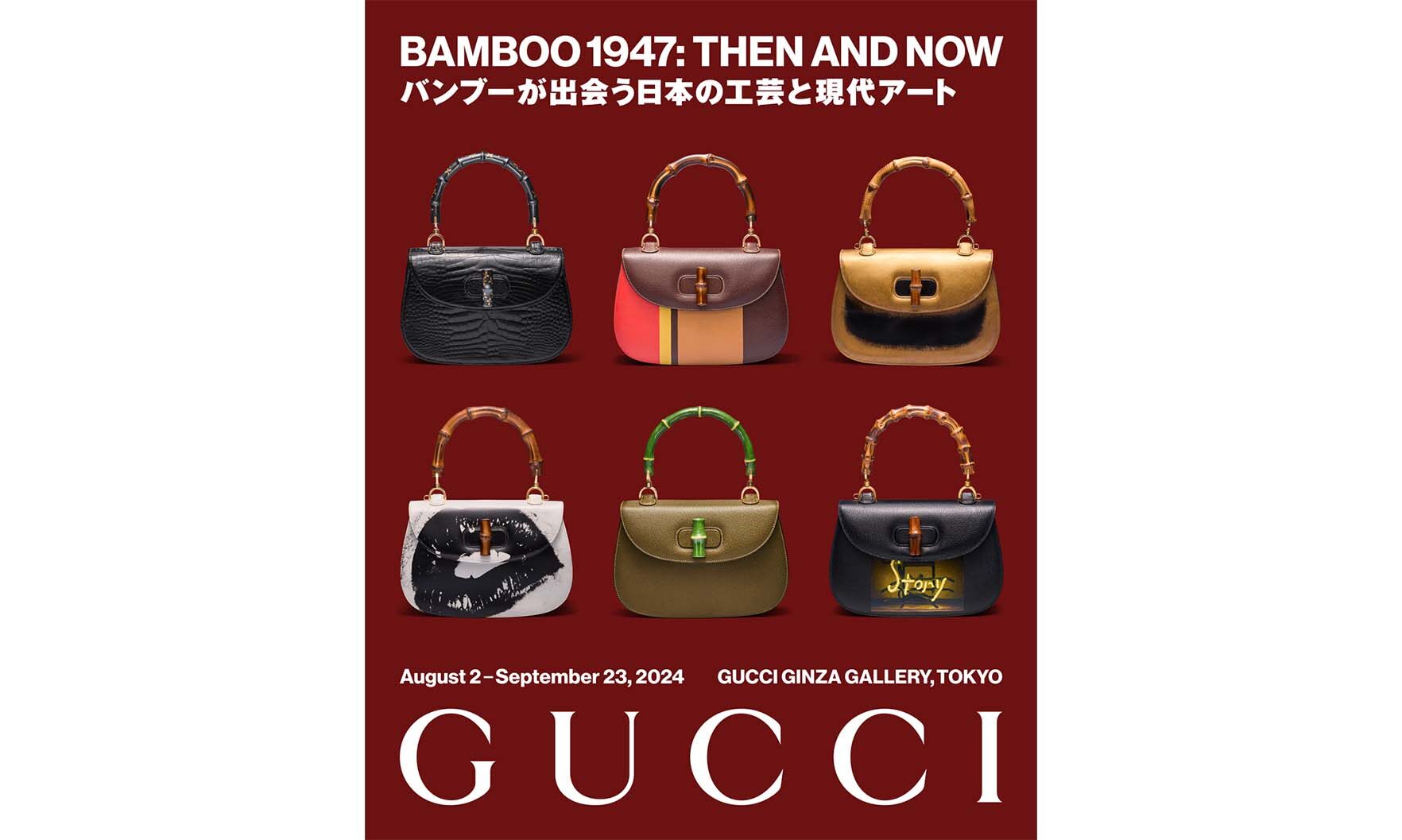創造主ヴァージル・アブローのつくりし世界に我々は生きている

午後、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)の早過ぎる死を知り、ショックを受けた。悲しみの一般表現としての「ショック」という程度のものではない。目の前が真っ白になり、これからどうしていいのかが分からないという真のショックを感じた。
今この記事を書いている私のオフィスの片隅では、クリエイティブディレクターであったヴァージルが「LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)」の最新コレクションとメルセデス・ベンツとの2度目のコラボレーションを発表する予定だったマイアミに持って行く荷物を詰め込んだスーツケースが、運ばれるのを待っている。
8年前に編集者になってからの私のキャリアの中で、ヴァージルに関係することがどれほど多かったかが思い起こされる。そのヴァージルが、亡き人となったのだ。
この投稿をInstagramで見る
我々Highsnobietyが追い続けるファッション業界という世界でヴァージルは、太陽のような存在であったし、今もそうあり続けている。現代のヴィジュアルカルチャー、ラグジュアリーブランド、そして拡大し続けるトリッキーな「ストリートウェア」の世界は、彼という太陽を中心に回ってきた。
ヴァージルは長らく、ファッションというこの文化的空間において、自身のプロジェクトを拡大させ、数々のコラボレーター(その多くが、キャリア発進からヴァージル自身が手がけてきた面々だ)と手を組み、Sharpieのペンの筆跡で数多くの多国籍企業に命を吹き込み、その才能で何千何万ものクリエイティブ人材を触発し、あるいはそれを超えて羨望や不信感さえをも掻き立てるほどの、全能の存在であり続けてきた。
ヴァージルの無数の才能の中でも最も重要だったのは、点と点をつなぐ能力であった。WhatsAppグループ、飛行機、様々なコラボレーション相手という宇宙の中で、彼は常に様々なアイデアを織り交ぜていた。人間Wi-Fiとでも言えば良いだろうか。単独のアーティストというよりは、人やアイデアの大きな波を動かす周波数のような存在であった。

2019年初頭、私はヴァージルについての口述記録に取り組んだ。彼の友人やコラボレーター、合わせて60人近くに取材し、彼のキャリアを解き明かすという内容だ。
それは幾重にも驚くべき体験であった。特に驚くべきは、取材対象となった誰からも、彼について熱烈かつ敬虔な言葉しか聞こえてこなかったという事実だ。
想像してみてほしい。
まず自身の人生について思い描く。そして、それを100倍速にし、100倍の人々と100倍の交流をしたと想像する。その状態で10年以上ずっと、誰の気分も損ねることなく過ごすことを想像する。
それこそがヴァージルと交わることの魅力だった。実際にそれぞれの人と共に過ごせる短い時間の中で、彼は常に100%の精神的余裕と100%の敬意を見せていた。
そんな優しさに加え、彼の仕事に対する猛烈な姿勢には、たちどころに人を感化するものがあった。
誰よりも熱心に、情熱的に、他の誰にも掻き立てられないような集中力で、人生をかけたプロジェクトに取り組んだ。週90時間労働は彼にとってごく普通であった。国やプロジェクト、ビジネス、分野を超えた対話を常に行うのが当たり前の毎日だった。
暗いワーカホリックでは決してない。止まることを知らない自己実現のためのプロセスとしてそんな生活を送っていた。彼の人生はそれ自体がひとつの作品であった。彼と対話をする経験には、彼が、彼のみぞ知る脚本をもとに壮大な旅を続ける中、しばし足を休める時間に立ち会う、というような、そんな感覚があった。

私自身ヴァージルの世界を巡る小さな旅の中で、彼の作品がいかに実質的に、彼自身のみならず、他者のためにも、障壁を破壊し続けてきたかということを認識するようになった。会話の中でヴァージルは、自らの仕事を「オープンソース」にするという発想について一貫して語っていた。
最初にその言葉の意味を尋ねた時の彼の回答は以下の通りだった。
「子供達が自分の服を見たときに『これなら自分にもできる』と思えるような、説明書一体型みたいな作品にするという意味だよ。ラルフローレンのスクリーンプリントのシャツでも、木の葉の落ちるパリのユネスコビルで35のルックを見せることでも同じ。分かりやすく言えばスケートボードみたいなものだね。誰かがこれまで誰も見たこともないような技を見せたとしても、その動画をYouTubeにアップすれば、世界各地の10人くらいの子供がすぐに全く同じ技をマスターする。それがオープンソースだよ。僕はそれでいいと思ってる」。
ヴァージルは、ただ単に何かを達成するのではなく、そのプロセスを世間に対して全面的に見せるような方法で物事を達成することを目指していたのだ。LOUIS VUITTONの就任記念ショーでレインボーのランウェイを歩き、かつての上司、カニエ・ウェスト(Kanye West)と涙ながらに抱き合った瞬間もそうだが、この発想こそが彼の成功を力強いものにした。

ヴァージル自身が成し遂げたもの自体のみならず、彼がまったく新しい、それまで不可能に思えたことを、誰にでも実現できるものへと変えてみせたという事実こそが、多くの人に感銘を与えた。
アルバムジャケットのデザインから始め、最終的には独学でプレタポルテコレクションのデザインを手掛けるまでに上り詰めることも可能なら、若者文化によってラグジュアリーの定義を刷新することも可能。大手ブランドで黒人初のクリエイティブリーダーになることも、自分のやり方で進み、世界の方を自分の型にはめていくことさえ可能なのだと、ヴァージルは身をもって示した。
そして権力の頂点に達したとき、ヴァージルは単にモノを作って売ることに終始せず、文化産業の原則を書き換えた。
消費者が王様であり、コンテンツが力を持つこの時代(ヴァージルはかつて私にこのことを「消費者の反乱」という表現で語った)において、彼は、いかに強力なアイデアを生み出し、デジタルの世界においてその効果をいかに高めるかについて本を執筆した。ヴァージルがこの10年、クリエイティブディレクション、ブランディング、広告の分野において残してきた足跡の大きさは、「シュールレアリズム」と聞けばサルバドール・ダリ、「ロックンロール」と聞けばエルビス・プレスリーを思い起こすのにも匹敵すると言えるだろう。
ヴァージルは、マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)が自分の弁護士だから、とよく言っていた。デュシャンによるレディメイド(既製品)を使ったアート作品作りに着想を得て、既に存在しているものにシグネチャーの鉤括弧を付けることでそれを新たな自分の作品にしてしまうという概念が許された気がする、ということを意味しての言葉だ。ヴァージル自身に自覚があったかは分からないが、彼が他のアーティストに対して新たな可能性の扉を開いていった点もまた、デュシャンに通じる部分だ。

ちょうどデュシャンが、ジェフ・クーンズ(Jeff Koons)やデビッド・ハモンズ(David Hammons)に対し、バスケットボールやバスケットボールのゴールのリングを「彫刻」に変えることを許したように、ヴァージルもまた、彼が生み出した型の中で世界を再定義していくであろう(そして既にしつつある)新世代のクリエーターを生み出した。
その世界とは一体どのようなものか?
ヴァージルが創造した世界は、デジタルライフが疎外感ではなく新たな可能性を生み出し、アート、建築、音楽、映画、ファッションが、これまで行われていた区別やジャンル分けなどが無意味に思えてくるほど自在にぶつかり合う世界、大企業も、創造性の敵ではなく、刺激的な新しいパブリックアートのパトロンとしての役割を果たすようになる世界だ。
かつてカルチャー業界を外から見つめる立場にあった独学の人材、リミキサー、グラフィティアーティスト、スケーターその他のルールブレーカー達が力を手にすることのできるような世界を、ヴァージルは作った。そして何より、iPhoneひとつで誰もが、次世代のアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)、アーサー・ジャファ(Arthur Jaffa)、レム・コールハース(Rem Koolhaas)、バーバラ・クルーガー(Barbara Kruger)、そして次のヴァージル・アブローになることができる世界を創り出した。
ヴァージルを正当に評価することは、今こうして彼の遺したこの世界に生きていくこととなった我々の使命だろう。
- Words: Thom Bettridge
- Translation: Ayaka Kadotani