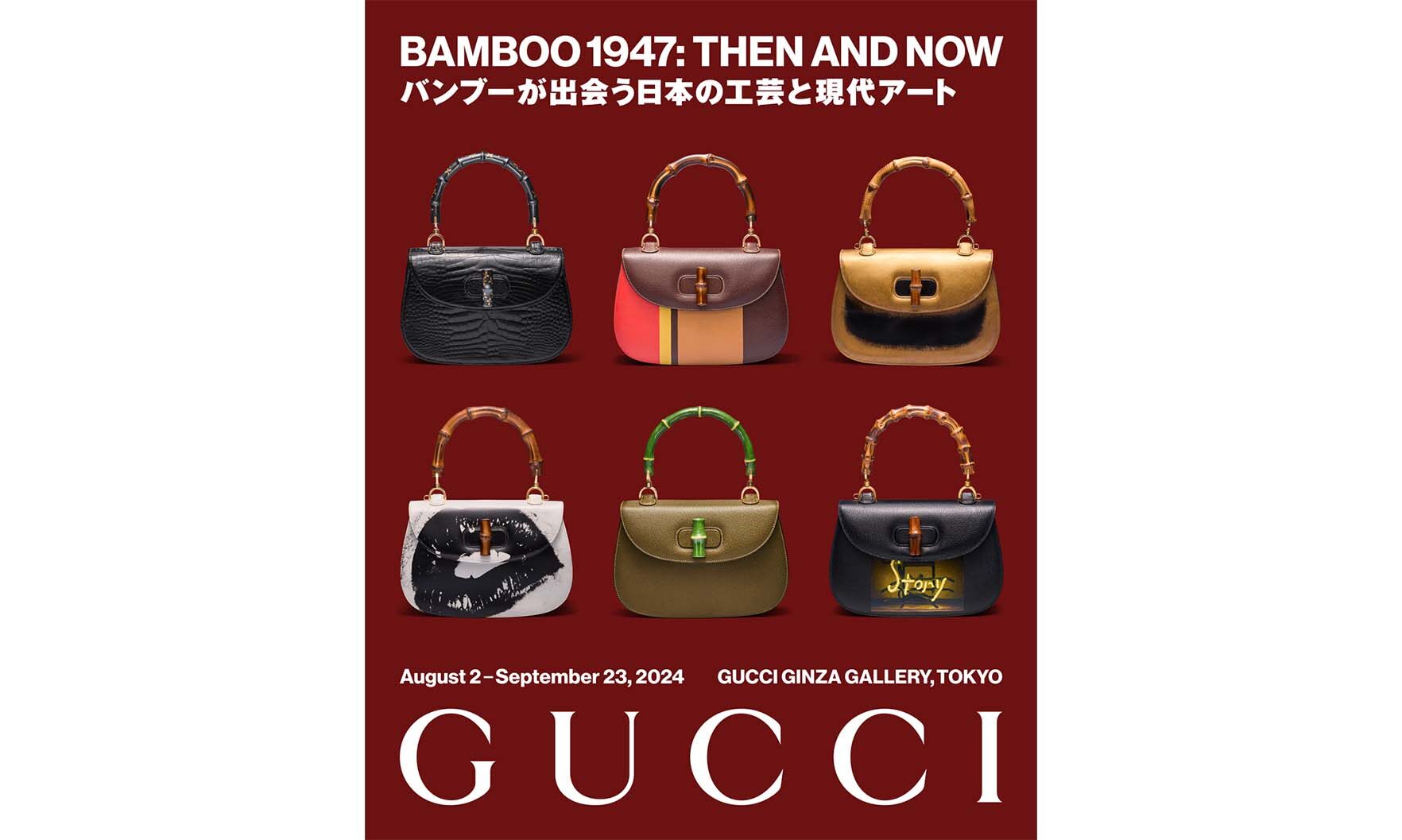美とエネルギーの探求者、we+が見る未来の糸口

※本記事は2023年9月に発売したHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE11に掲載された内容です。
we+(ウィープラス)はものごとに基づいて新たな視点を与え、価値を創生するコンテンポラリーデザインスタジオだ。自然や社会環境と共存しながら、定義づけられる以前の感覚や価値観、違和感すら美しく形にしていく。彼らは発動するエネルギーの一つひとつに目を向け、その影響力のベクトルまでを繊細に感じながら組み立てていく。ソリューションを提示するのではなく問いを形にする彼らの美徳、その背景にあるものとは。ファウンダーの林登志也氏と安藤北斗氏に話を聞いた。
社会への違和感というファウンデーション
we+は、デザインを通じて利便性を促進したり様式を定義するためではなく、価値観を広げるためのきっかけとなるものを作り出す。彼らのアウトプットの形は様々だが、作品は一貫して圧倒されるほど芸術的であり、それらは全て奥深く幅広いリサーチを経て力強く裏づけられる。Artistic Researchによって構築された彼らのコンテンポラリーデザインは、果てしないほどの工程を要しながら形を与えもののあり方や考え方をつくり出す。彼らが作るものや、工程そのものがこれからのデザインのあり方やものづくりへの考え方の根底に訴えかけてくる。
——安藤北斗さんのプロフィールには、視点と価値の掘り起こしに興味を持ったとのことですが、どのようなきっかけがありましたか?
安藤 出身は山形のとても保守的なエリアではあったんですが、両親が大学の教員で元々非常にリベラルな考え方をする人間なんです。学校教育を真正面から受けとめず、違った切り口で受け入れてもいいのではなかろうかと言うタイプでした。それが普通と違うと気づいたのは僕が大人になって結婚してからなんですが、1+1=2という回答に限らなくてもいいんじゃないか、というようなあまのじゃく的な発想は小さな頃から持っていた。それがおそらくある種の原点的なものだったりするのかもしれないですね。
——最も影響を受けたアーティストは?
一番インパクトがあったのは高校生の時に出会ったオノヨーコさん。鑑賞者と作品が一方通行というアートの認識をサクッと打ち砕いてくれましたね。ひもといていくと、60年代ぐらいからのフルクサスという前衛芸術の運動をされていて、ジョン・ケージ(John Cage)やナム・ジュン・パイク(Nam June Paik)達もその流れ上にあったと思いますが、僕の中で既存の文脈に対してカウンターとなったアートの代表格です。
——林登志也さんは、舞台演出業・広告会社を経て、デザインリサーチを基点とする作品制作へ移られました。古来の生活風習への興味関心が強かったのだとか。
林 先住民文化とか縄文文化に興味を持ち始めたのは20代の中盤くらいからなんですが、きっかけはとにかく気持ちが苦しかったことです。僕らは生まれたときから特に足りてないものはないけれど、経済活動ってモノをつくらないと生きていけない。世界中で環境破壊が叫ばれている一方で、企業は経済活動をしているという違和感に折り合いがつけられなかったんですよね。そんな中、先輩に青森県の縄文遺跡の世界遺産登録のプロモーションの手伝いをする仕事に誘われたことがきっかけで、縄文時代に光明を見たんですよね。


——それぞれ全く違う背景のお二人が一緒にやるようになったきっかけは?
林 黒﨑輝男さんがIID世田谷ものづくり学校でスクーリングパッドという学校をやってたんです。僕は20代の悶々期にそちらに通ったのですが、いろいろなところからいろんな変な人がたくさん集まっていて、そこで出会った友達が安藤と友人だったんです。2005から2006年のことですね。
——組織化にあたりどのようなヴィジョンを共有していましたか?
安藤 厳密にステートメントとしては出してなかったですが、モノが飽和している状態が僕達の世代以降であって、デザイン業界の先輩方が密接に結びついていた産業はこれから明らかにシュリンクしていくと言われていたので、ものづくりに対する疑問や問いが間違いなく僕らの中にはありましたね。少子化や環境問題などの背景がある中で、生活のために自己矛盾をはらみながら経済活動に加担しているというシチュエーションに対してこれからどうしていくべきかを真剣に考え始めていたタイミングでした。

コンテンポラリーデザインの基点となるアーティスティックリサーチとは
——we+にとってターニングポイントとなったのは?
安藤 2014年に『MOMENTum(モメンタム)』という作品をKAPPESというコレクティブとしてミラノで発表したんです。当時我々が感じていた不安や焦燥に対して、好きなものを作って世の中を驚かせよう、とノリに近いモチベーションで作った作品が、デザインブームというメディアでその年のミラノデザインウィークのベストテンに選ばれたんです。その時、あるフランス人のキュレーターから「これってコンテンポラリーデザインだね」と言われたことをきっかけにしてその意味を掘り下げていきました。どうやら自分達がやろうとしていることはこの文脈に乗っかってくるんじゃなかろうか、とそこから輪郭がぼんやり浮かび上がってきたんですよね。その後、試行錯誤をしたりいろいろな人に会いに行くことで、コンテンポラリーデザインのなんたるかが見えてきた。だから我々のステートメントが明確に固まったっていうのは2016〜17年なんですけど、一番最初のきっかけは2014年ですね。
——コンテンポラリーデザインの定義をどう捉えていますか?
安藤 いま存在するデザインの本流をただ更新していくということではなくて、支流をどんどん作っていくということなんじゃないかと思っています。今までになかった視点や切り口、考え方でデザインに対峙して、デザインを更新していくことであり、そうすることによってデザインのみならずそれを享受する人達の感覚も含めて、デザインが豊かになっていくということではないかと。ライターの土田貴宏さんが執筆された『デザインの現在コンテンポラリーデザイン・インタビューズ』も同じように定義していて、僕も100%賛成しています。
林 デザイン史を見るとバウハウスやメンフィスなど全てカウンターパートで各国から新しい動きが出ています。2000年代からコンテンポラリーの大きい潮流は実は生まれていて、今はそれが大きくなっている過程であると見ています。現在のコンテンポラリーデザインもまた、メインストリームに対する反動として存在してきているんだと思います。
——表現の基点となるアーティスティックリサーチとは何ですか?
安藤 主観的に選んだものに対して自分達の手を動かして、絞り込んでいくことで、深掘りしていくこと、かな。
林 その後、それを伝えるときの伝え方に工夫をするっていうことだと僕は思うかな。手法がなんであれ感覚を総動員させて自分達が得てきたものを伝えるっていうことが多分アーティスティックリサーチのアーティスティックたるところなのではないかと。見せ方についても完成形だけ見せるのが今までのやり方だったけれど、その過程もちゃんとフィールドワークの様子やプロトタイプを通してみせるっていうことが、最近面白いのかなと思っています。
『Nature Study』という霧をテーマにした個展を1年前にやったときに感じたんですが、実験的にアウトプットのみならず、スタディの過程で起こった感情を整理していったんです。すると、今までのようなデザイナーや興味ある人達以外の科学者や別のフィールドの方にも届く感じがしたんです。この裾の広まるような感覚はもっとブラッシュアップさせていきたいなと感じました。
安藤 アーティスティックリサーチとは手法でも目的でもなく、取り組み全体のことだと言えるね。僕達はアウトプットを決めて逆算することはなくて、まず目の前の素材や現象、考え方をどんどん膨らませていくんです。いろんな実験を経て、いろんな方向に持っていきながら、コンテキストを見直したり、ロジカルにリサーチを進めていきながら深掘りをしていく。すると、あるタイミングでその素材や現象がどういう見せ方をすれば一番よく見えるのかを導いてくれる。先が見えない怖さもありますけれど、最近は自分達のアプローチを理解してくれるクライアントも増えています。


ゆらぎの美学に潜むwe+の表現哲学
——we+の表現芸術においては、圧倒的な美しさに自然というコンセプトが常に融合しています。『MOMENTum』では、水の性質を活用して有機的な没入感を演出しました。ミキモトのウィンドウディスプレイでは、真珠が貝の中で結晶層を形成していく過程から着想を得て尿素の飽和水溶液を気化・結晶化させ、雪のような繊細で美しいツリーを作り上げました。物質を突き詰め、感情を呼び起こさせるほどの芸術にまで押し上げている。表現におけるこだわりはどんなことですか?
林 作品をつくる限りは共感してもらいたいのですが、自然現象ほど気持ちをハッとさせたり心を震わせたりするものはないと思っていて。言葉や世代が違っても、あの水の動きを見て驚かない人はほぼいないのではないかな、という感覚が自分達の中にあるので、自然の揺らぎや不確実性をいかに捉えるかがすごく有用だと思っています。
最近では、自然に限らず廃棄物を都市の素材と見立てて作品を作っていますが、先日、深澤直人さんが僕達の作品を見てくれて、「素材を素材以上に見せるようなアプローチだな」といった感じのことをおっしゃっていました。自然現象についても同じことが言えると思っていて、自然現象の中でも心が揺れ動かされる部分を自分達なりに抽出している感覚なんですよね。素材にしても、一番ここが魅力的なところだというものを煮詰めて差し出したような感覚かもしれません。
安藤 僕達は不確実性という言葉をよく使うんですけれど、揺らぎというのもほぼイコールなものと捉えています。均一なものに対しての興味はほとんどなくて、工業製品のように均一なものよりも、揺らぎを持っているものの方が共感されやすいんじゃないかという気がしていることもありますね。少し表情のあるコンクリートの表面ってずっと見てられるじゃないですか。それもおそらく自然の揺らぎということなんでしょうね。
あとは、僕らwe+のメンバー内はもちろん、クライアントや工場の人とか、実際作ってくださる方々が常に同じ目線でいることは重要かなとは思っています。責任の所在は明確にしつつもヒエラルキーはなくして、どうみんなで作っていけるのかを考えることはとても大切だと捉えていて。we+のチーム内でも立場関係なくフラットにいいものを作れる環境を意識的に作っています。みんな自分の意見にあまり固執することがなく、デザインの方向性を決める基準は好みではない。ある程度クライテリアを明確にした上で進めると勝手に導かれるものなので、意見がぶつかるときはどちらが最短距離かっていう時くらいなんです。



we+とはどのような立場で何を提案しているのか
——近年は廃材を都市の土着の素材として活用した活動にも積極的です。この活動はwe+にとってどのような発見につながりましたか?
林 クライアントのオフィスをリニューアルする時に、廃材から新しいマテリアルを作ろうというプロジェクトがあって、それがひとつのきっかけにはなったんだと思いますが、その過程で畑から野菜を取ってきて調理するような感覚があったんです。非効率的であったり足りないものが多かったりするんですが、その作業を通して社会の仕組みが持つ課題を認識することができました。都市の廃材シリーズでは実際工場に出向いて現場の方々にヒアリングしながらものづくりをしようとしているんですが、世の中にはただリサイクルすればいいといった風潮もある中で、それぞれがなんのためにあるのかという視点を持つことの大切さを自分達が体験することで感じられた。社会の仕組みの複雑さや危うさに目を向けることで、世の中で有耶無耶になっていることへの問題提起につなげることができました。
安藤 おそらくデザイナーが社会に求められてることって刻々と変化してると思うんです。先輩達のデザインが我々の世代にとってちょっと違うように、時代とともに求められる内容がどんどん変化してきて当たり前だなと思っています。今自分達が行っているリサーチプロジェクトも、半分意識的にあるいは半分無意識的に社会を日々観察して、そこから受ける影響が多分すごく素直に出ている結果なんだろうなと思っていますし、5年後、10年後、20年後には社会の情勢に合わせて自分達の役割も変わっているんだと思います。



——『Refoam』は発泡スチロールが100円ショップの商品などへリサイクルされる過程における複雑さに着目し、中間処理工場で再生発泡スチロールの新しい価値を提案しながら、リサイクルの流れをシンプルにしました。サステナブル産業への美しい問題提起と言えるのでしょうか。
安藤 元々あまりサステナブルという文脈で捉えてはいないんですよね。廃材シリーズはどちらかというとクラフトとのつながりや交わりのような考え方です。例えば陶器が地元の土に強く紐づくように、東京のデザインスタジオである我々が強くコネクトする素材はなんだろうと考えた時に、それは都市が生み出す廃材だといえるんじゃないかという仮説のもとにプロジェクトを始めてるんです。産業廃棄物工場でリサーチをしていくうちに少しずつ問いが立てられていく。なので多分、自分達が今何を言うべきなのかとか、自分達の主観であったりとか、何が面白そうだったりとか、そういう極めてプリミティブなモチベーションなのではないかな、という印象はあります。
——工場に出向くことはプロジェクトの更新に欠かせないんですね。
林 廃材の工場にずっと行っていると、最初はネガティブな印象を持つような匂いや視覚的なものもだんだんと気にならなくなってくるんです。発泡スチロールを溶かしたなんだかすごく面白い素材が見つかって、それについてよくよく聞くと、リサイクルはしているけれどすごく旅をしているとのことで、すごくモヤモヤして、その場で作ればいいじゃんって作っていったり。工場で再利用のために素材が選別された後に残った山から素材をピックアップして作った『Remains』というオブジェもあるんですけれども、山はガラスの小さなくずや陶器のくずの集合で貝塚みたいでよく分からないけれどすごく面白いなと思ったんですよね。それはやはり行ってみないと分からないし、一次情報に触れて自分で何かを感じることは一番大切ですよね。最近一番生きてるなと思った瞬間が、ガラスの破片の山にバケツを持って入ってゴミをピックアップした時なんですよ。
安藤 確かに。普段は命の危険を冒してまで危ないところでガラスを拾う必要がそもそもないからね。産廃の処理工場とか匂いとかもそうなんですけど、スタジオ全体として自分達のコンフォートゾーンからどんどん抜けていこうとする欲求みたいなのがとても強いのかもしれないです。今まで見たことないものにどんどんチャレンジしたくなるし、考え方もどんどんスライドしていきたいし。コンフォートゾーンを抜けなくてはとみんな無意識に思っているかもしれない。
we+が社会のためにできること
—— “芸術は、自然や生活の模倣であると同時に、逆に生活のインスピレーションになりうる” と言葉がありますが、we+の在り方は、どのように捉えることができるんでしょうか。
安藤 あまり僕らは生活に自分達の活動をコミットさせることはないですね、我々のものづくりって生活に密接しているものではないですから。地面を生活に例えるとそこに根ざしている木ではなくて、遠くから援護射撃している雲に含まれた雨といいますか。雨みたいなものがどんどんとその地面に降り注いで、地面に栄養を与えていく。当然なくてはならないものだとは思うんですけど、ある種、異分子みたいなものじゃないですか? ちょっと嫌なものっていうかね。違和感だからこそ生活に対して別の視点を与えていくものというか、そういった存在なのかな。
——既存の仕組みを覆し、持続可能的な社会を作り出すことができると思いますか?
林 できると信じたいんですけどね。僕らは社会を変える大きな歯車にはなれないけれど、一番最初に回り始める小さな歯車みたいな役割ならできるんじゃないかなって気はするんですよね。現実から言うと、何に役に立つのか分からないんだけれど、ここが回らないとその次は絶対回らないみたいなものってきっと世の中たくさんあると思うんですね。
安藤 小さい歯車から大きい歯車、そういう意味で確実に社会に接続した存在でありたいね。ただその一番最初のきっかけというか、視点を作っていくことに対してはかなり意欲的にコミットしていると思っています。自分達の中で浮かんだ素朴な疑問や視点をどんどん作っていきたいなと思っていますし、そういうものをどんどん投げかけていきたいですね。


——デザイン界では社会問題の解決にコンセプトが偏りすぎていること自体が問題だと言う声もあるようですがどう思いますか?
安藤 デザインで社会に対して警鐘を鳴らしていくことは、もちろん大きな役割としてひとつあると思うんですけど、やはり僕らの場合、共感してもらえることにプライオリティが置かれるべきだなと思っています。メッセージだけだったり、コンセプトだけだと多分人って受け入れてくれないんですよね。人の気持ちを動かしていくこともデザインの持つ大きな機能のひとつだと思っていますから。やはり、美的な神秘的な美しさには正面から向き合っていくべきだし、ものづくりの精度が高くないと結局誰も受け入れてくれないから、そこはやっぱり忘れるべきじゃないと思います。
——we+の圧倒的な美を作り出すのに最も必要な要素は何でしょう?
安藤 やっぱり、見つかるまでやるっていう根性論ですかね。
林 手法としては根性論みたいなところありますが、なんのためにやってるかみたいなことですかね。問題解決に特化するとデザインが説教臭くなる。本当は楽しさとか充実感みたいなものとつながってるものだとは思っていて、単純に美しくて魅了されるものを作ることは楽しいからじゃないのかな。及第点取れてたら世の中には出せるけど自分達がつまらないから、その少し先を目指したいんですよね。不十分な状態でアウトプットするのでは、世の中に対して僕らがコミットしている意味がないし、それなら作らない方がいいのではないかという感覚すらありますよね。

The Thinking Pieceとは
——社会問題に訴えかけるデザイナー達の作品をキュレーションして、その売り上げをウクライナに寄付する活動、The Thinking Pieceを2022年にスタートし、今年はミラノのデザインウィークに出展されました。この活動の目的はなんですか?
安藤 デザイナーとして社会課題に対して何か寄与できることはないだろうかというところから始まり、2022年はあのような形になったのですが、ひとつ後ろに走らせてるコンセプトとしてコンテンポラリーデザインに向き合っている方々と一緒にやっていくっていうのがあったんですよね。我々の活動と近い動きをしているデザイナーが面になって見えることは、デザイン界においても重要なことなのかなと。
2022年はドネーションという目的があったのですが、23年のミラノでどんなメッセージを発するべきなのか、プロジェクトの発起人でもあるライターの土田貴宏さんとTAKTPROJECTの吉泉聡くんと我々の4名でたくさんのディスカッションを重ねました。我々が言いたいことは問いなのか、解決策なのか。結局『Obscure solutions(あいまいな解決策)』をテーマにしました。つまり、ひとつの事柄でもいろんな解釈ができるし、いろんな切り口がある。それらをひとつに絞りきってしまうことがある種、ネガティブなことなんじゃなかろうかということも含めて、各デザイナーがそれぞれの問いを立て、それに対して各自の視点でアウトプットを提示するという構成にしたんです。
その背景には、ソリューション系のデザインが飽和しつつあり、そうじゃないデザインってなんなんだろうとずっと考えていたことがあります。ダイレクトに社会に結びつくかどうかよりも、そうではないところにもデザインの価値はあるはずだという我々の仮説をそのまま軸にしてみたんです。
——今年のミラノで、総合的な気づきはどんなことでしたか?
安藤 僕が感じたのは、一般的な意味合いでのサステナブルはもうインフラ側にまわりつつあること。そこに加えていかに新しい視点があるかどうかですね。それができていた人はすごく面白いと思いましたね。
林 毎年、動向やココは行くべきだみたいなものがある程度ひとつに収斂していく印象だったんですが、今年はあまりそういうのがない印象でしたね。デザインの流れがリキッド化したような感覚がありました。プレゼンテーションの仕方やコミュニケーションのユニークさは以前にも増して重要度を増し、もうモノだけでは正直語れないという感じはあります。どういう流れの中でステイトメントを出しているのかが複合的に判断される傾向にある。そういう面からもますます継続していくことの重要さを改めて思いましたね。瞬間的に評価されることももちろん大切ですけど、そういった評価は長期的にはもう意味をなさなくなっているのかもしれません。

- PHOTOGRAPHY: YUYA SHIMAHARA
- INTERVIEW: YUKA SONE SATO