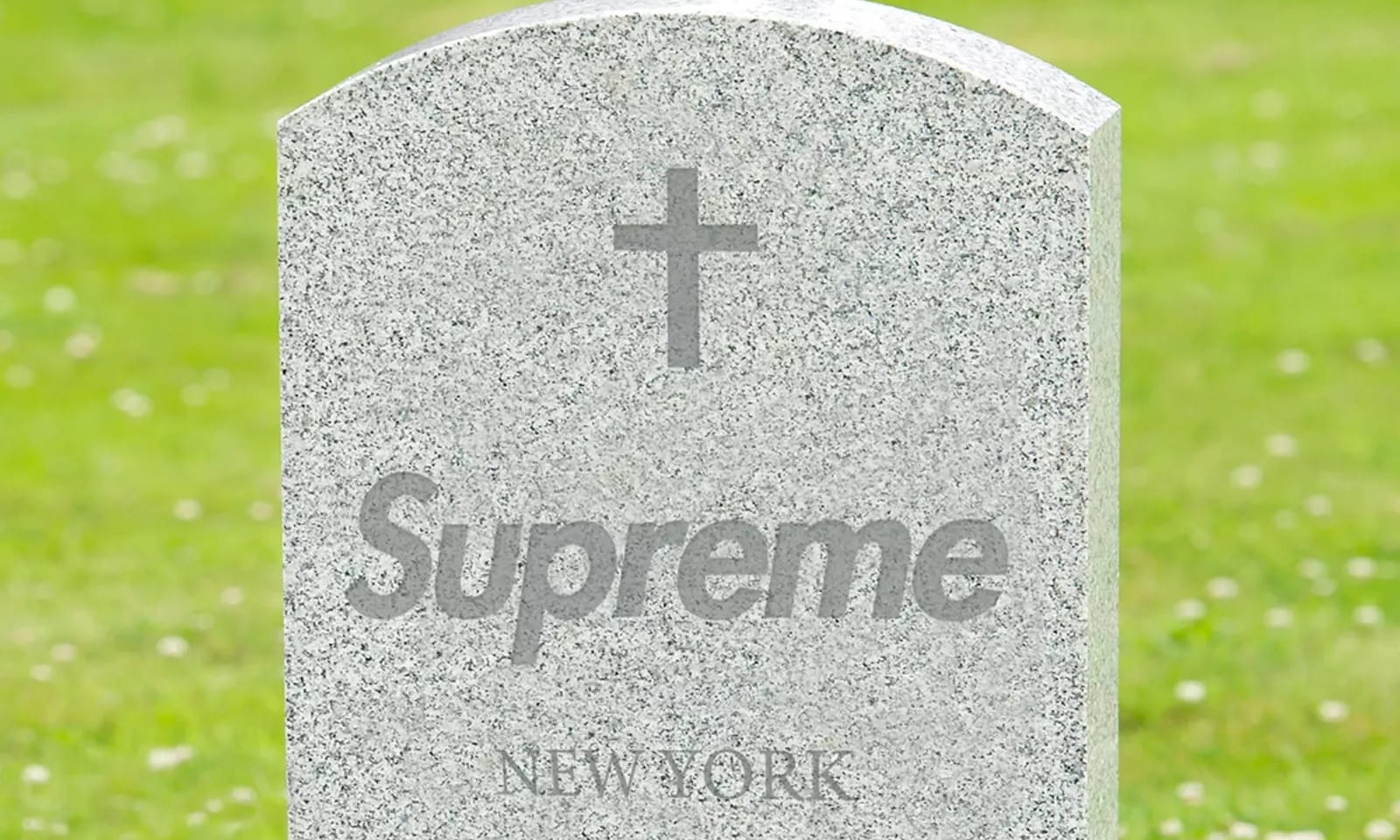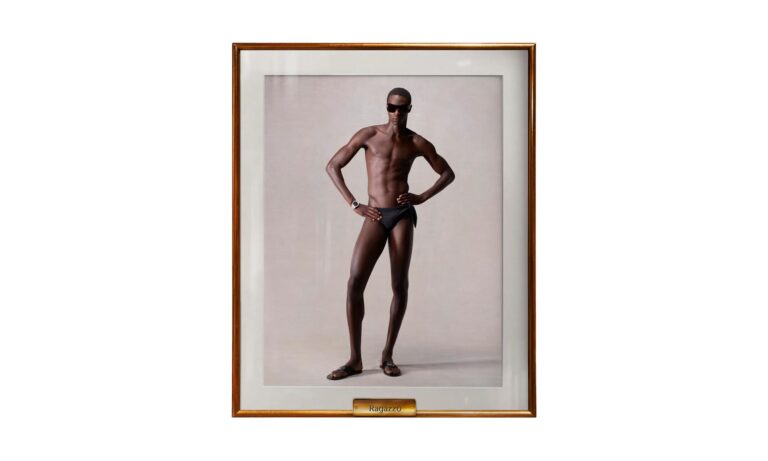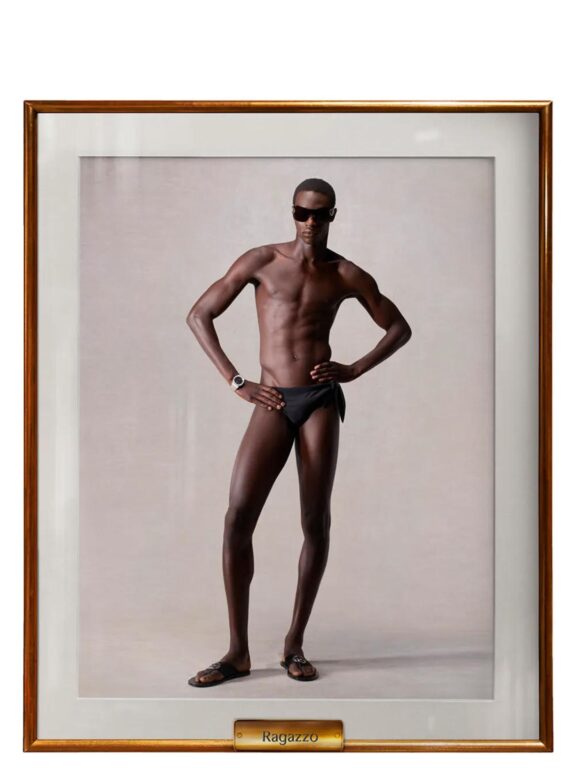style
Supremeはやはり終わりなのかもしれない
Supreme(シュプリーム)はやはりいよいよ本当に終わりなのかもしれない。筆者の予測不足だったとは言わせない。
2023年のSupremeの終焉を示唆した記事では、うっかりちょっとした騒動を呼んでしまった。しかしその時は弔いの鐘を鳴らすつもりではなく、今日のストリートウェアシーンにおけるSupremeの立ち位置を定量化しようと試みたに過ぎなかった。
Supremeは単に、あまりにも大きな存在になってしまい、クールでい続けることができなくなったことで、ストリートウェア用語で言うところの「終わり」を迎えてしまったのだ。
ストリートカルチャーにおける妥当性の希薄化、強力な挑戦者ブランドの台頭、売れ行き低迷、ブランドの企業化といった動きの中で、Supremeはもはやストリートウェアの最前線には安住できないという見方を私はしていた。私の記事の後には同様の記事が多数続いた。それ以外の面でも、私の見方が正しかったことは、時が経つにつれてますます明確になった。
私の記事の掲載から数カ月後、Supremeの親会社であるVFコーポレーションが、Supremeブランド分の数百万ドルを含む収益悪化を発表した。さらにSupremeの新クリエイティブディレクター、トレマイン・エモリー(Tremaine Emory)が、組織による人種差別を主張し退社。大きな物議を醸した。
その間もSupremeは、企業側の需要に応えるべく、かつてないほど積極的に事業を拡大していた。この2年で上海、韓国、シカゴ、ベルリンの各都市に旗艦店をオープン。上海、韓国、シカゴ店舗はこの1年の間に相次いで誕生している。以前のSupremeであれば、新店舗のオープンは5年に一度程度のペースだったはずだ。
外から見ると、これまで寡黙だったSupremeが、時間を取り戻そうと王座を主張し、かつて支配していたものの今や若手の新進デザイナーらにすっかり侵食されたストリートウェア市場の縄張りに、何とかもう一度入り込もうと躍起になっている姿のように感じられた。
心配になるような有様だ。

5月中旬のWWDの記事には、VF社が現在Supremeの売却を検討している旨も報じられている。
この噂についてVF社側は肯定も否定もしていない。Highsnobietyがコメントを求めたところ、同社の担当者は「市場の噂や憶測についてはコメントを控える」との回答であった。
ただSupremeの売却に衝撃的な部分はない。VFコーポレーションの新CEO、ブラッケン・ダレル(Bracken Darrell)も、投資家に対し、VFコーポレーションの経営陣に「批判の対象とならない者はいない」と語ったばかりだ。
現在約50億ドルの負債を抱え、数カ月前にも収益悪化を発表したVF社だが、2020年のSupreme買収額は20億ドル以上であった。
さらにVF社は2023年のSupreme収益予測として、前年を遥かに上回る6億ドルを掲げていた。
しかしSupremeの売上は、前年の5億6,100万ドルから7%減の5億2,300万ドルまで減少した。

CEOのダレル氏はVF社の負債対処に本腰を入れた。2023年6月の就任後数カ月でバッグブランドのEASTPAK(イーストパック)とJanSport(ジャンスポーツ)の売却に踏み切った。またアナリストらからはTimberland(ティンバーランド)を売却した場合に利点が生まれるとの論議も上がっている(現在Timberlandは売却されていない)。ダレルはまた目に見えて揺らいでいるVANS(ヴァンズ)にもテコ入れしている。
しかしSupremeは30年の歴史を持つブランドであり、VF社はSupremeに干渉はしないと買収当初から約束していた。
当時のVF社CEOスティーブ・レンドル(Steve Rendle)は、買収発表直後の2020年11月のインタビューで「Supreme事業は経営レベルが高く、非常に成功しているため、ライトタッチな統合とし、Supremeはこれまでと同じ運営をし続ける。我々が介入し何かを変えるということは考えていない」と述べていた。
Supremeからさっぱりと手を引くことで、介入をしないという当時の約束をVF社が果たす形となることも十分に考えられる。
その可能性のほどは分からない。しかし売却が現実味を帯びるほどの状況に、今日のSupremeが陥っていることは確かだ。
ただVF社が実際にSupremeを売却することになった場合、それはニューヨークのスケートブランドSupremeにとって活力を取り戻す絶好の機会となるかもしれない。再び別の上場企業の所有下に入りさえしなければ、の話だが。
Supremeは現在、かつてのSTÜSSY(ステューシー)のようにストリートウェアの霞の中にいる。しかしSTÜSSYはSupremeがもがいている間に、賢明なリブランディングを行い、カルチャーの最先端へと飛躍を遂げた。生彩を欠くSupremeとは対照的に、Stüssyは軽快だ。
AIME LEON DORE(エメレオンドレ)の再活性化のときと同じく、小型化こそ要されたとは言え、STÜSSYが生まれ変わったという事実は、ストリートウェアの世界において「終わり」の後に「復活」の可能性があることを感じさせる。
しかしSTÜSSYが民間企業であるのに対し、現在のSupremeは親会社、投資家の意向に応えなければならない立場にある。投資家は成長を好む。より多く、より大きく、を望む。より多くの利益を目指すこうした企業、投資家の意向は、本物のクールさとは対極を行く。
整理されたイメージに根ざしたブランド理念を持つSupremeのようなブランドにとっては不都合だ。
はっきりさせておこう。「Supremeは終わった」という言葉は決して、Supremeがもはや存在しないとか、儲からないとか、Supremeの終焉を早過ぎると嘆く層に対してさえもはや物欲を掻き立てないとか、そういう意味で放たれているのではない。まだそうした力は残っている可能性がある(残っていると言い切っても良い)。
Supremeの純利益はざっくり6400万ドルと、今でも利益を上げていることは明確だ。しかしストリートウェアにおいて金銭的な力は、単に事業を継続する程度のことにしかつながらない。それよりも真に重要な影響力、悪名、顧客からの忠誠心は、金銭では手に入れることのできないものだ。業績を論じる度に何百万、何千万ドルという単位の話になること自体、Supremeというブランドが手に余るほど巨大なものになっている事実の裏返しだ。
ストリートウェア用語において “dead”(終わっている)という言葉は、“passé”(流行などが終わっている、過ぎ去っている)、 “out of touch”(共鳴しない、時代とずれている)、あるいはティックトッカーズらの言うところの “cheugy”(ダサい、古い)といった言葉と同義であり、かつては新鮮さがあったものの今は尖りを失ってしまったブランドを揶揄する意味で使われる。
かつてSupremeを「終わった」と称していたのは、そのほとんどが、自らが気に入っているブランドの知名度が上がることを喜ばなかったSupremeファンだった。自分たちを置き去りにしていったSupremeに、ファンは腹を立てた。しかし腹を立てつつも、当時のファンはSupremeがストリートウェアの頂点に君臨するという事実を否定できなかった。
今は違う。
かつて挑発の代名詞であったSupremeの名前も、今ではひとつの組織を指す名称に成り下がってしまった。ストリートウェアにとっての今のSupremeの存在。人の一生において避けられない死や税金のように、疎ましくも避けられない存在となっている。
- WORDS: JAKE SILBERT
- TRANSLATION: AYAKA KADOTANI