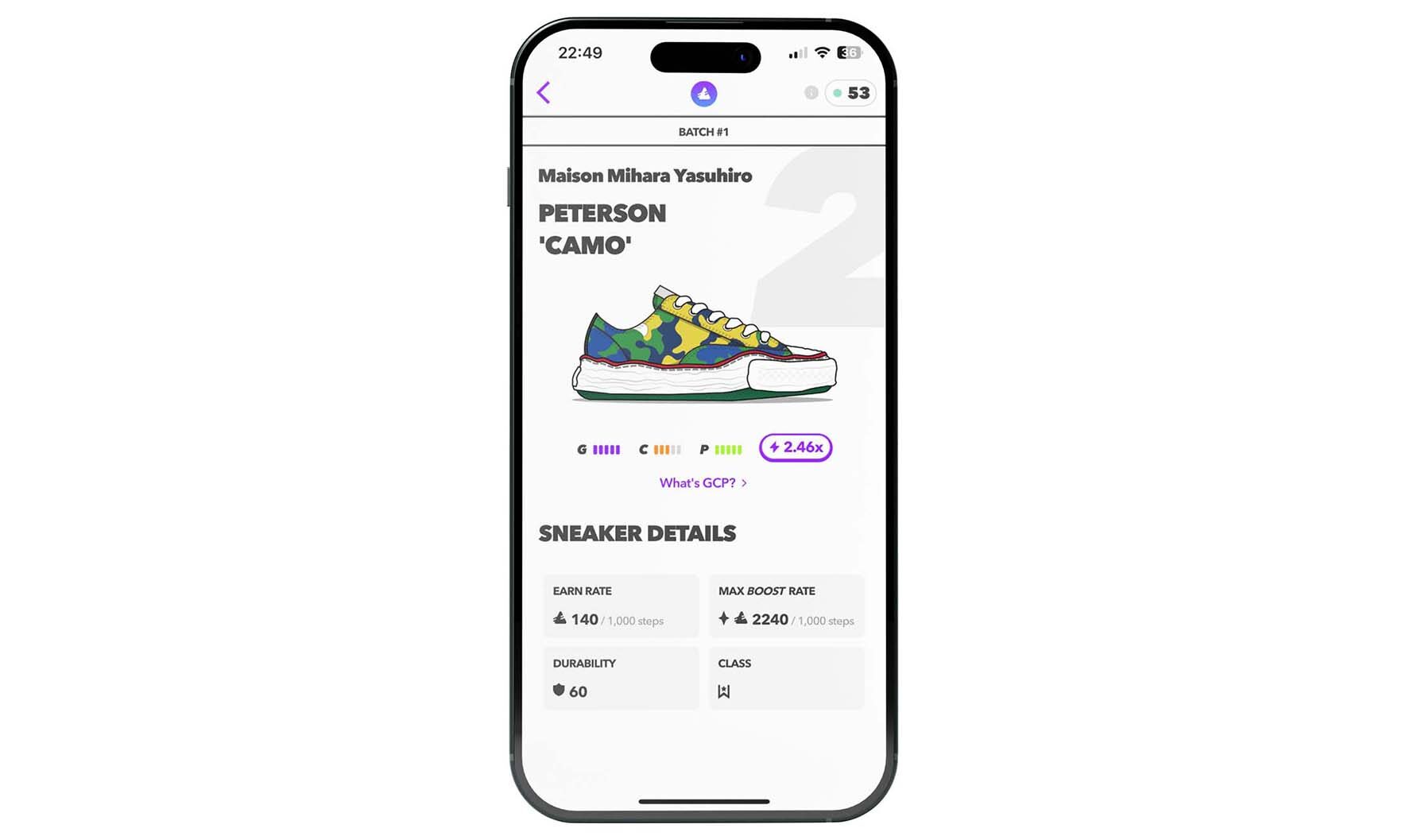パリでのゲリラ的邂逅から1年後、三原康裕と山岸慎平が机を囲んだ

激動の2020年がひとまずの節目を迎えようとしている年の瀬、新宿区にある「MAISON MIHARA YASUHIRO(メゾン ミハラヤスヒロ)」のアトリエに向かった。その道中で「BED J.W. FORD(ベッドフォード)」の山岸慎平と落ち合い、大量のヴィンテージ・ミリタリーウェアにハット、壮観なブックシェルフ、アートから動物の骨までさまざまなタイプのオブジェクトに囲まれた、三原康裕のワークスペースのドアを叩いた。彼らは、世界的パンデミックが起こる、ほんの少しだけ前に行われた1月のパリ・ファッションウィークのランウェイショーで「ゲリラ的に」交わった二人である。
2020年1月17日の「パレ・ド・トーキョー」までさかのぼる。「MAISON MIHARA YASUHIRO(メゾン ミハラヤスヒロ)」の招待状を片手に、30脚のイーゼルが並ぶショーフロアに辿り着き、ゲストは皆が皆、三原のファーストルックを待っていた。チェロの音色が会場を包み、ランウェイに現れたのはエレガンスを志向し、コーデュロイ素材で仕立てられたツーピース。フリンジがなだらかに踊る、男の姿である。それは、限られた者しか知らなかった「BED J.W. FORD」の2020年秋冬コレクションだった。衣服のオーセンティシティを解体し、アイロニカルな視点から、時代や社会に溢れる記号やイコンを軽妙に再構築していくMMYとは、明らかに嗜好が異なるコレクションに胸騒ぎを覚えたゲストも少なくなかったに違いない。15人のモデルがバックヤードに戻ってすぐ、劇的な空間の変質と時を同じくしてMMYのショーの幕が上がったのだった。
前例のない数十分間のセッションの起点を、正確に綴ることは難しいようだった。たびたび三原は、「お兄ちゃん(彼は山岸のことをそう呼称する)はパリで発表した方が良い」と言ってきたそうで、信頼しているメンターからの言葉が記憶に刻まれていた山岸は「オンスケジュールの場でブランド名や評判にこだわらず純粋に服を見てほしい」と思ったことを契機に、話を持ちかけたのだという。こうして生まれた提案を全面的に受け入れた三原が、自身のショーが始まるまでの時間を彼に開放したのだ。
「僕はお兄ちゃんに対して安心していることがひとつあります。情熱があるんですね」と、三原は口火を切った。
「クリエイションという、枯渇しそうな情熱を燃焼させていく作業で、すり減らない人はいない。それでも僕は、生きている価値を見出している。はじめてパリでやった時には、残酷なぐらいの賛否両論があった。いろいろなことを聞かれるし、『日本人だから』というだけで御三家からの影響を問いただされたこともあったね。ただ、僕はそうしたことがすごく気持ちよかった。実は日本人としてのアイデンティティはパリが教えてくれたところが少しある。アメリカの服で育ったからか、ヨーロッパの文化に何かしら『間違った』解釈があってそれを壊したモチーフを使ったりすると、日本のジャーナリストは一切触れてこないけど、パリの批評家たちはすぐに指摘する。ヨーロッパ人よりも繊細に服を作っているお兄ちゃんがパリでやった方がいい理由はいくつかあるけど、自分の作ったものに自信を持つ上で、評価されるか、されないかという俎上にあがり自信がなくなるほどにメタクソに書かれる時も必要だと思ったからですね。彼らの姿勢の根幹は、クリエイティブの本質があらわれることを期待しているところにある。ファッションのシステムは90年代、2000年代、現在と変わってきているけど、厳しい目線を持ったジャーナリズムの熱心な担い手は、さまざまな国から、まだパリに集まっている」

2018年6月に「ピッティ・イマージネ」の招待デザイナーとしてランウェイショーを行い、翌シーズンからミラノでコレクションの発表を続けてきた山岸は、「僕の経験くらいでは、まだ多くを語れませんが」と思慮深げに前置きをして、コレクションをパリで披露した意味を確かめるように言葉をつむいでいく。
「感覚的に、パリの方が僕の話をしっかりと聞いてくれるムードを感じます。力を貸してくれる方々の気質や、クリエイティブに向かっていくチームのまとまり、アイデアひとつで膨らんでいくフォーマットの自由度に楽しさを覚えますね。言語化しようとすると上手くまとめられないんですけど、単純に、パリにいるほうが寂しくない。国というよりは人。僕には、パリの方が、ミラノに比べて頼れる人達がいます。少なくとも今、パリという場所に望むことがあるとしたら、かつて僕が思い描いたパリであり続けてほしいという願望が一番にありますね」
「僕が『PUMA by MIHARAYASUHIRO』で3年近くミラノで発表していた経験があるから、ファッションの体制的な面、またスタッフとショーを作るという側面でパリとの違いをよく知っているんですね。簡単に言うとイタリアは、オペラの国。洋服にあてる照明ひとつの演出についても、行間を読む日本人とはまた違い、伝わらないことが実に多い。スーツの哲学が根強く、ものづくりに長けた国のファッション界には伝統的な保守性があって、クリエイティブを評価する視点だけ見てもインディペンデントなブランドがショーをしづらい環境ではある。トレンドを重視し、いささか排他的で、商業主義な部分があるから、僕は違う『ゲーム』の遊び方を考えてパリに立ち戻った。僕自身はとても楽になったね」と三原は話し、山岸は大きく頷いた。
「もうすぐ50代になるんだけどさ」と物づくりにあててきた時間の長さを思い起こさせながら、飄々と話を続けた。「お兄ちゃんもそうだと思うけど、自分が思ったものが形になった時の喜びって最初の時からずっと変わらない。一種の中毒性もあるけど、そうやって作り続けていく中で自分のことを賛否してくれる人々がいる環境はやっぱり良い。文化としてファッションを捉えてくれるからこそ、僕はパリを自分の居場所なんだと感じることができる。とはいえ、最近は不愉快なことも多くなってきた。悪いことばかりでないと分かっているけど『ファッションゲーム』のルールが変わり、SNSの存在感が大きくなり、クリエイションがどうこうではなく、何やらタグ付けされることに躍起になり、あらゆるスピードが重視されているからね」

矛盾やパラドックスを愛し、アイロニカルなユーモアを「一種のマナーと同じだ」と語るデザイナーの言葉を借りるなら「表現に敬意があり、ショーをやる意味を真摯に捉えられていたかつての時代」は、オフスケジュールのショーがパリの各所で行われていた。「それはアンチモードの時代。ビッグメゾンのショー会場の前でやったり、セーヌ川のほとりで真冬にモデルを立たせたり、ね。熱量を共有したいと思えば、インビテーションなんて無くてもよかった」。しかし、スケジュールが一定の時間で刻まれ、細やかに管理された現在のファッションウィークの期間で、そうした選択をするブランドは激減の傾向にある。時間以外の何かにも追われているかのように、忙しく動き回るジャーナリストの背中を想像できるかもしれない。そうした中で、自身のスタンスについて「自分のために服を作っているが誰かを不快にしてはいけない」と語ったことのある山岸が、「服をみせる」ためにオンスケジュールの場を志向することは自然なことだった。しかし、いかに見せるか。彼は、服づくりのアティチュードと重ね合わせながら語る。
「基本的に、人としての根っこに優しさみたいな部分、人の気持ちを考えたり、汲み取ろうとする姿勢がないと誰かに何かを伝えづらいですし、意味も込めにくいと僕は考えています。ある種、世間に対して『分かってたまるか』と、強い意思や熱意を抱いくことは簡単。もちろん、僕なんかにもありますしね。ただ、大事なことは、ちゃんと理解してもらうために誠実に向かいあう姿勢です。人と向き合うことは、SNSの断片だけじゃなく、時間をかけてコアな部分を掘り下げ、熟考すること、そこで熱が帯び、理解してもらいたいことに説得力が生まれるのだと信じています。それがある種の “可能性” に変わるかもしれない。古くさい気もしますけど、デジタル全盛の時代に必要なことって人間としての温度みたいなものをちゃんと作品にのせることができるかだと思っています。三原さんの美学にも、哲学にも、凄くひんまがった正直さと正義があるし、デザイナーである僕はそれに救われている。三原さん自身と、クリエイションでみせる、笑いながら作られる不規則な違和感。それを当たり前にしていく作業に素直に尊敬の念があるんです。三原さんの洋服と伝え方には、先に述べた温度のような、確かな『らしさ』みたいな熱をちゃんと感じ取れる。僕にもしっかり伝わってくる。三原さんに限らず、そういったデザイナーが僕は好きだし、憧れを持っています」
「パリを利用して伝えたいことがある」と言い、髪をかき上げた三原が、グローバリゼーションとテクノロジーの現代的な功罪をクリティカルに指摘していく。「時代が移って、携帯が手元にあってインターネットに繋がっていれば、努力をしなくても簡単にグローバリズムのシステムを手に入れられるようになった。それまではローカリズムが確かにあって、80年代でいえばビッグブランドの隣で、日本人やアジア人がアンチモードとしての違和感をパリに与えてきた。SNSで自分たちで発信できるようになって、夢に描いていたはずのグローバリズムを手に入れてしまい、安易に認められるようになると、それが途端に安っぽくなった。しまいには、コンプライアンスというものもある。それがネガティブを排除する動きだとしたら、ある種の『タブー』が分かりづらくなった時代と言ってもいい。唯一、残っているタブーは、宗教的なこと、人種的なことであったりする。そういうものだけが浮き彫りになっているように思えるんですよ。本来、そうしたことを互いに認め合うためのグローバリズムという概念だったはずなのに、文化の盗用を揚げ足をとるかのように瞬く間に指摘するシステムにさえなっている。要は、グローバリズムを使いこなせなかったということなんだよね」

「あのショーについて、いろいろと聞かれましたよ。僕は彼らに、日本の若いブランドが勝手にショーをやりやがったんだと言いましたけど」と笑う三原は、「この仕事をしていて、自由であったり、本物になりたいと思う気持ちがなくなったら、僕はもっと違うことをやっているかもなとたまに思うんですよ」と言う。
「時代を変えるということを意識していない、ということはない。自分が描きたいと思っている人間像の中には、不条理や、人の弱さというのが内包されている。実際に自分が大人になっても欠点ばかりが出てくるわけだけど(笑)、そういう類の人間らしい美しさを感じられる時がある。後悔がない人間なんて、なんの魅力も感じないね。僕はバカでダメな人ほど好き。人生が幸せなことだけではないと誰もが分かっているし、語れるほど大きな夢もないけど、『可能性』を広げたいんです。とにかく嫌なのは、釣り堀に餌を投げるような場所やものづくり。人が求めるものより、バカなことを本気でやる人がいるんだと、人が魅了されることをやりたいんですよ」と三原は話し、「お兄ちゃんは何者かわからない『ミステリアス風味』があるよね。僕の場合はもう『インタビューを受けません』だとかしない限り、その風味を出せないわけよ」という。その言葉のシニフィエ(意味するもの)が、ずっと無秩序に逆立ったままだったヘアにあらわれているのではないかと勘ぐっていると、「そうするとさ、インテリジェンスが垣間見えるわけよ。ほら、僕なんかただの変わったおっさんだよ」と三原が口にすると、「愛すべき、ですよ。僕は少しだけ歳をとって素直に感情に向き合えるようになった気がしますが、人気者、もっと言うと『メジャー』に憧れるようになりましたね」と山岸が阿吽の呼吸で返事をした。
予定調和のない対話を耳にしていると、MMYの2020年秋冬コレクションのショーノートに綴られていた「『普通』が表なら、必ず人間には裏面がある」というセンテンスが1年前の記憶から音を立てて歩み寄ってきた。今回の機会の創出者で、柔らかなコートを羽織ってアトリエを後にしてしばらく経った山岸は、「ファッションをただの流行にしないためには問題提起する場である必要はあると思っている」と語っていた三原について、あるいは、自身の今後を反芻するかのように、こう語り添えた。
「三原さんの姿を見ていて常に感じさせられることがあります。変わらない熱量を持つことって当たり前に思われがちですけど、実は、すごく難しくて、体力が必要で、いわば、情熱のスタミナが試される。三原さんの熱はいつも変わらない。ストイックともまた違い、もっと当然のこととして楽しんでいる感じがするんですよ。裏では数え切れない葛藤があることはわかっているんですけど、パリのコレクション前日の忙しい時でもあまり表に出さない空気だとかは、たまんなく素敵だなと思いますよ。僕は、洋服のことをずっと考えてるんですけど、それがファッションを考えるにすり替わると少し疲れてしまう。ようやく最近になってシンプルに自分が憧れたファッションと近い方法で、いけるとこまでいくと決めました」
思えば、佇まいも異なるふたりのデザイナーと机を囲んでいた時間、MMYが名を連ねるパリのデジタルファッションウィークの発表がすぐそこに控えていることなど考えつく間もなかった。いくばくかのアイロニックで、しかし、どこまでも粋な時間の虜になっていたのだ。
- Photography: Genki Nishikawa (MILDinc)
- Words: Tatsuya Yamaguchi